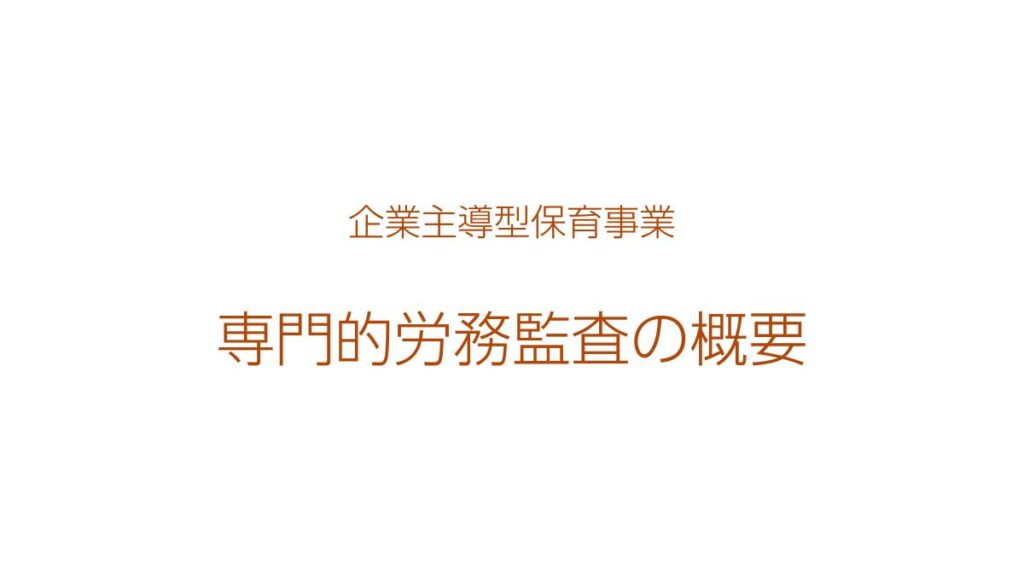🎯 労務監査の目的と基本原則
目的
専門的労務監査は、保育施設職員の「労務環境」や「処遇改善」を重点的に確認し、職員が働きやすい職場環境を整えることで、保育の質の向上を図ることを目的としています。
基本原則
- 主体: 公益財団法人児童育成協会(協会)が、こども家庭庁からの委託を受けて実施します 。
- 協力義務: 助成を受けた事業実施者(施設運営者)は、協会および再委託機関が行う監査に積極的に協力しなければなりません 。
- 再委託: 協会は、こども家庭庁の承認を得て、監査業務を第三者に再委託することができます 。実際の労務監査は、各都道府県の社会保険労務士会に委託し、実施されていると考えられます。
🔎 労務監査の実施内容
1. 監査の視点と法令
- 保育士等の職員の労務環境・処遇改善を中心に確認します。
- 公平・中立に実施し、保育提供に支障のないよう配慮します。
- 監査は労働関係法令等および「専門的労務監査評価基準」に基づき行います。
- 立入調査が原則ですが、必要に応じて遠隔調査を実施することもあります。
- 原則2名以上の監査員で実施し、身分証を携帯します。
- 監査通知書(様式1)が事前送付され、労務監査確認書類一覧表(兼自主点検表)を提出します。
- 監査拒否は認められません。
2. 実施方法と準備
- 事前通知: 原則1ヶ月前に事前通告されますが、事前通告なしや期間を短縮して実施されることもあります 。
- 拒否不可: 事業実施者は、監査の対象となった旨の連絡を受けた場合、その実施を拒否することはできません 。
- 調査・質問対象: 施設の設置者や運営の責任者だけでなく、必要に応じて保育従事者やその他職員等からも事情を聴取します 。
📋 監査結果の処理と是正措置
1. 指導と改善報告
- 現地講評: 監査終了後に講評・助言を行い、「専門的労務監査結果一覧表」で報告します。
- 必要に応じて改善通知書(様式3)が発行され、改善報告書(様式4)の提出を求めます。
- 改善内容には議事録や届出の写しなどの証拠資料を添付します。
- 改善が見られない場合は、助成金の返還や助成決定の取消しなどの措置が取られる場合があります。
主な指導の内容
- 文書指導: 改善を求める必要があると決定された場合、様式3の通知書により、1ヶ月以内の回答期限を付した文書指導が行われます 。
- 改善報告: 指導を受けた事業実施者は、様式4の改善報告書を提出しなければなりません 。これには、改善是正を検討・報告した際の理事会等の議事録の写しなどが添付書類として求められます 。
- 再監査: 改善状況を確認するため、または期限までに回答・提出がない場合は、必要に応じて再度専門的労務監査が行われることがあります 。
2. 重大な不正・違反への対応
- 措置: 複数回の改善指導でも改善が見られない場合や、監査の拒否・妨害、虚偽の報告、書類偽造などの著しい不正・違反が判明した場合は 、
- 協会は直ちにこども家庭庁に報告します 。
- 助成決定の取消しや、新規の利用児童の入所停止措置を含む必要な措置が講じられる場合があります 。
- 不正が疑われる場合は、こども家庭庁と協議し、弁護士等や労働基準監督署等と連携を図ります 。
3. 結果の公表
- 専門的労務監査の結果は、協会のホームページにおいて公表されます 。また、指摘事項が類型化・分析され、事業実施者に対する周知啓発に利用されます 。
その他
- 協会は各施設ごとに監査内容・結果を記録・保存します。
- 以前の監査内容を踏まえ、効果的な監査の実施に努めます。
- 不正が疑われる場合は、こども家庭庁・労働基準監督署等と連携して対応します。
- 助成取消しが生じた場合は、児童の受入れ先確保などの調整も行います。
- こども家庭庁との協議を経て、運用上必要な事項を定めます。
まとめ
専門的労務監査は、保育施設で働く人々の「安心と働きやすさ」を守る仕組みです。
法令遵守だけでなく、処遇改善や働き方改革の推進にもつながる重要な取り組みです。
職員の労働環境が整うことは、子どもたちへの保育の質の向上にも直結します
(参考)専門的労務監査の主な指摘事項
関連ページ
関連ページをもっと見たい方は、下記より戻れます。
ご参考
※ 専門的財務監査で指摘を受けた事項については、
必ずしも外部にすべてを依頼しなければならないわけではありません。
まずは事業者様ご自身で整理・見直しができるよう、
経理規程の見直しに関する説明書や、
発注規程・助成金取扱規程・積立資産管理規程などの
規程案をご用意しています。
「何から手をつければよいか分からない」
という場合の参考としてご覧ください。
企業主導型保育事業 各監査での指摘事項 令和4年度~令和6年度
下のリンクから指摘事項のページに進みます。
企業主導型保育事業に関する4コマ漫画
「まんがの部屋」コーナーでは、内容ごとに4コマ漫画で説明しています。