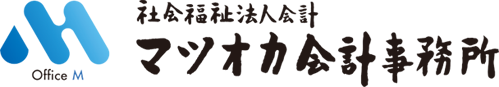会計公準とは──会計の“あたりまえ”を、社会福祉法人の視点で見直す
法人実体・継続事業・貨幣的評価──会計は3つの“前提”から始まります。
会計は「自由」ではなく、「前提」から始まります。
まずはその“あたりまえ”を、法人の立場から見てみませんか?
社会福祉法人でも会計の前提にある「会計公準」は、会計の“土台”となる考え方です。
このページでは、企業会計での3つの公準を紹介しつつ、福祉法人向けに読み替えてやさしく解説します。
会計は「自由」ではなく、「前提」から始まります。
まずはその“あたりまえ”を、法人の立場から見てみませんか?
社会福祉法人でも使われている「会計公準」は、会計の“土台”となる考え方です。このページでは、企業会計での3つの公準を紹介しつつ、福祉法人向けに読み替えてやさしく解説します。
会計の“前提”って、意識したことありますか?
会計とは、「ルールに従って記録して、報告する」もの――
そう思われがちですが、実はそのもっと手前に、“前提条件”があります。
たとえば次のような「当たり前」が、会計を支えているのです:
- この法人は、明日も、来年もサービスを続けるはずだ(継続性)
- 理事長の財布と法人の財布は別ものだ(実体の独立性)
- お金に換算できるものだけを会計に記録する(定量性)
これらの“前提”は、会計の世界では「会計公準(かいけいこうじゅん)」と呼ばれています。
会計公準とは──会計の“土台”を支える考え方
企業会計では、次の3つの公準が一般的に認められています:
- 企業実体の公準(Entity Assumption)
- 継続企業の公準(Going Concern Assumption)
- 貨幣的評価の公準(Monetary Unit Assumption)
これらは、「こういう前提があるから、会計処理はこの形になるのだ」という、いわば会計のルール以前の“あたりまえ”を定義するものです。
社会福祉法人なら、こう読みかえてみては?
会計公準はもともと企業会計の前提として整理されたものですが、社会福祉法人にも十分通用する考え方です。
そこで私たちは、以下のように表現を読みかえてみました:
| 一般的な表現 | 社会福祉法人向けの表現 | 説明 |
|---|---|---|
| 企業実体の公準 | 法人実体の公準 | 法人と理事長など関係者は別人格。お金も活動も区別する。 |
| 継続企業の公準 | 継続事業の公準 | 来年度以降も事業が継続されるという前提で会計処理する。 |
| 貨幣的評価の公準 | (表現は変更なし) | 会計に記録できるのは「お金で表せるもの」に限る。 |
このように読みかえることで、社会福祉法人の実態に即した会計理解がしやすくなります。
では、それぞれの公準について詳しく見ていきましょう
会計公準は、すべての会計ルールの「前提」です
この3つの前提があるからこそ、会計原則や会計基準といった「ルール」が成立します。
ルールを理解するには、まず“なぜそのルールがあるのか”を知る。
その答えが、会計公準なのです。