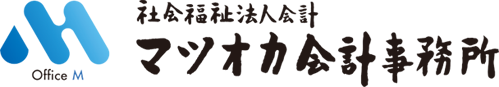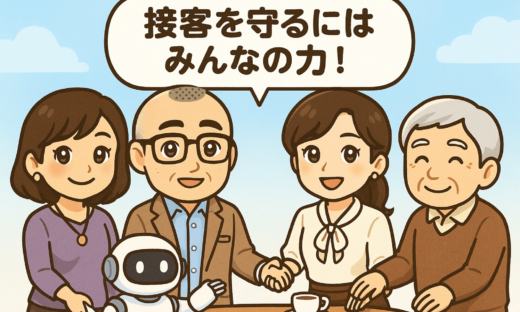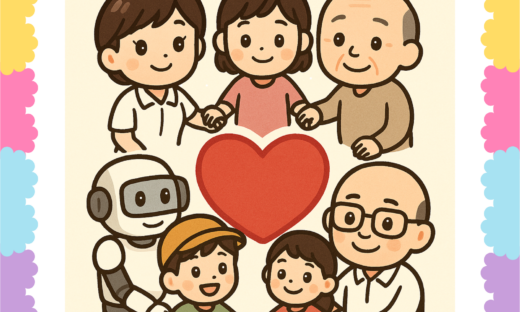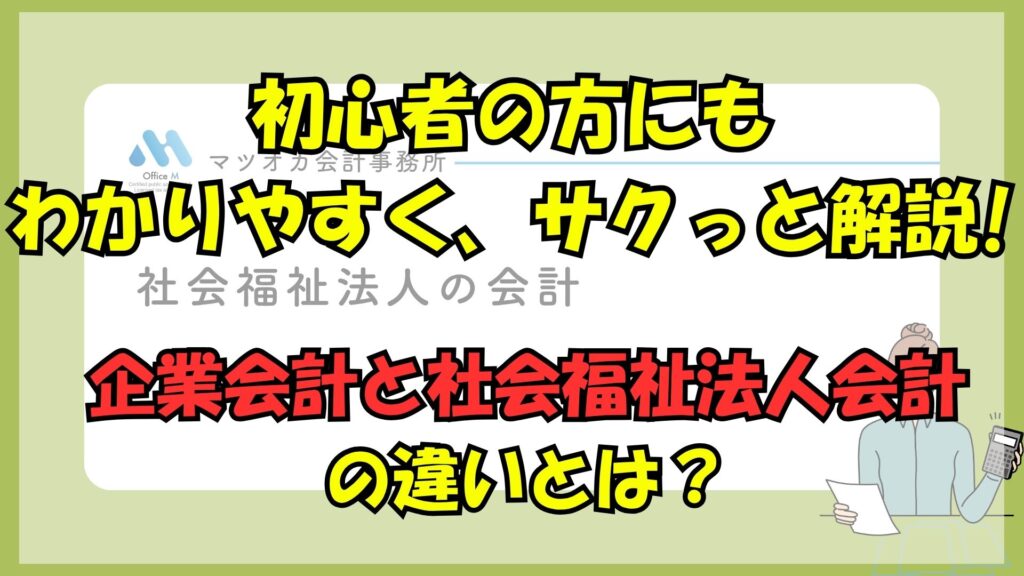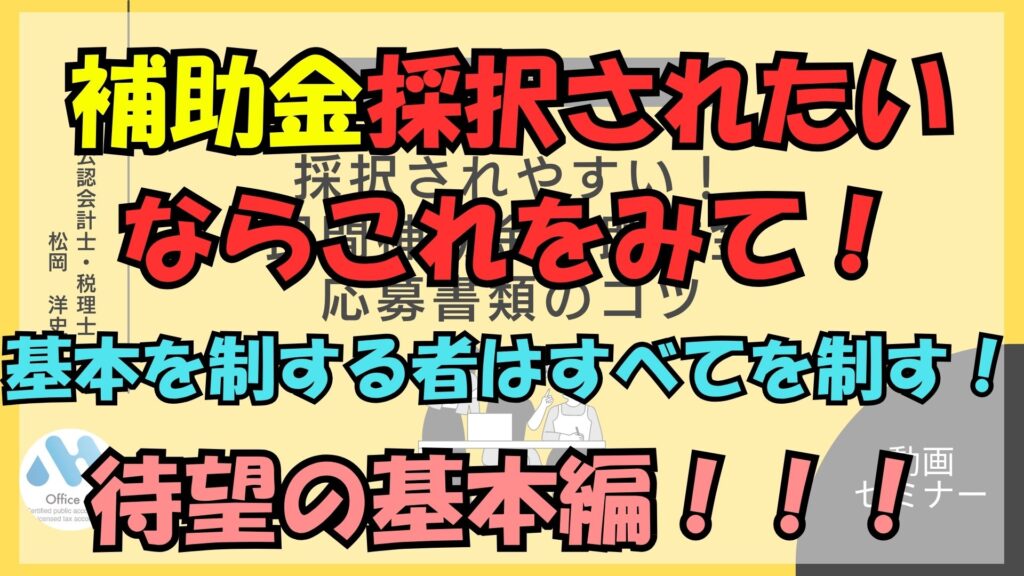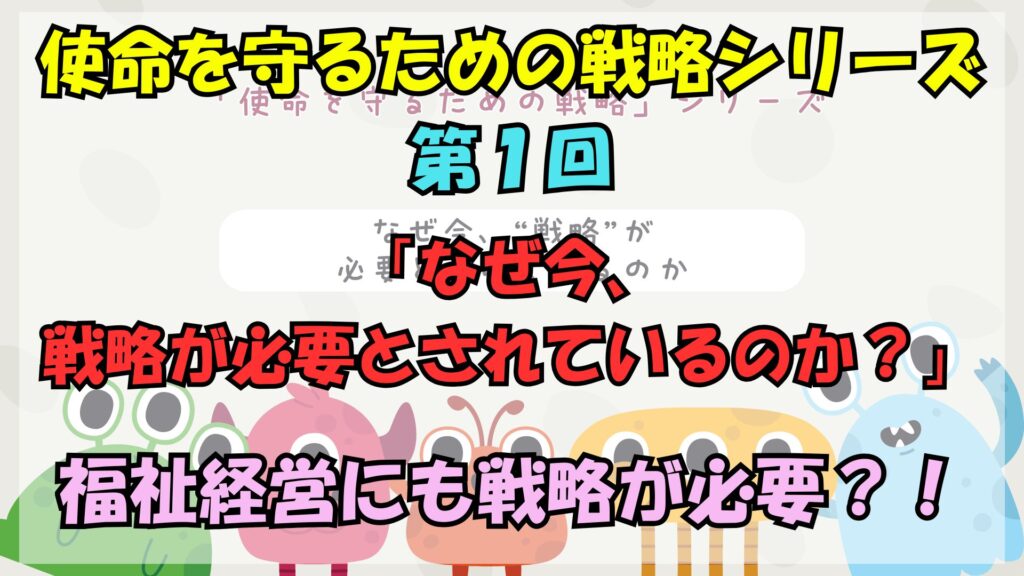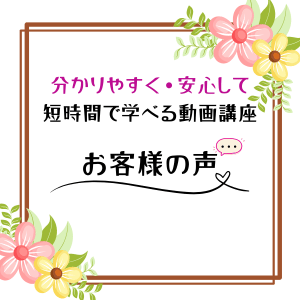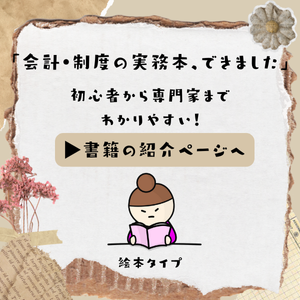「2040年、小売店が消える!?」たかしさんとおとはさんが解説する“販売の未来”
「貴重な売り場」が消える日?商品販売の労働力不足と解決策
🛒 はじめに:いつものお店が無人に…?
🟦 「ホームページ利用上のご注意について」
https://office-matsuoka.net/goriyouchui
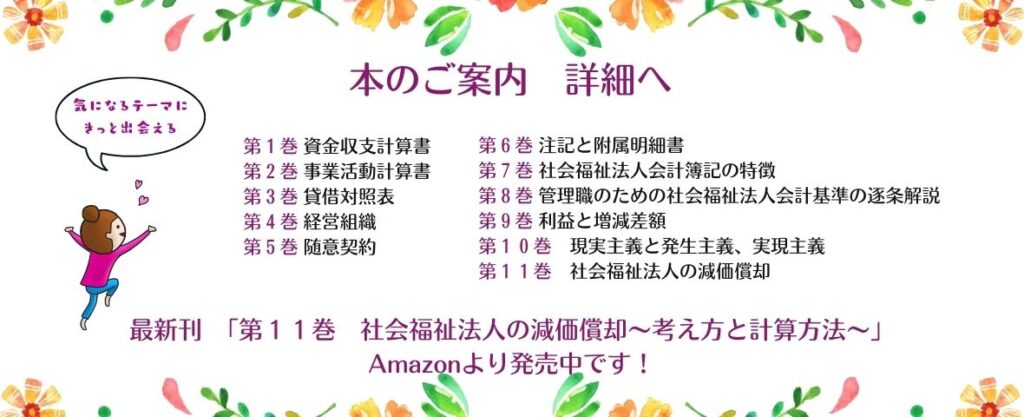
-1024x417.jpg)
こんにちは!
社会福祉法人会計専門の会計事務所代表のたかしと事務スタッフのおとはです。
今回は「商品販売の現場で進む人手不足」について、わかりやすく解説します。
この記事は、「「未来予測2040」労働供給制約社会がやってくる」(リクルートワークス研究所編)の内容を基に、接客サービスの希望的な2040年の姿を考察したものです。

「貴重な売り場」が消える日?商品販売の労働力不足と解決策
🛒 はじめに:いつものお店が無人に…?


やあ、おとはさん。この前いつも行ってた小売店、添付されてる自動レジだけになってたよ。

それ、もしかして労働力不足の影響かもしれませんね。日本全体で「労働供給制約社会」がすぐそこまで来ています。
‼️ 商品販売は「生活維持サービス」


商品販売って、生活に欠かせないサービスなんだよね。

その大切な分野で、2040年にはなんと約109万人も人が足りなくなるってご存知でしたか?
「未来予測2040 労働供給制約社会がやってくる」より
「商品販売」職種(小売店主・店長、販売店員、商品訪問・移動販売従事者などを含む)について、労働供給不足が予測されています。
•具体的には、2030年には40.2万人、そして2040年には108.9万人の労働供給が不足すると推定されています。
•2040年の労働需要(438.5万人)に対する不足率は24.8%に達すると予測されています。
🤖 解決のカギは「機械化」と「シニアの力」
【1】機械化・自動化で負担軽減
- セルフレジや在庫管理システムで人手を補う
- ロボットと人が協力する店舗運営が主流に

「未来予測2040 労働供給制約社会がやってくる」より
1.徹底的な機械化・自動化:
レジ業務は、スマートショッピングカートや無人レジの普及によって、今後大きく自動化が進むと予測されており、店員の仕事は顧客が会計を行う際のサポートや接客にシフトすると考えられます。
管理業務(本部への売上報告、値引き・返品対応など)も、デジタルサイネージやRFID導入による在庫管理システムの刷新によって縮減可能です。店長の業務も、デジタル技術を駆使した売り場づくりをする仕事に変わる可能性があります。
商品の陳列・補充業務は、そのすべてを人手なしで行うのは難しいものの、ロボットと人の協働が進む可能性があります。例えば、カメラ・センサーで欠品位置を従業員に知らせ、ロボットが商品を運び、従業員が陳列・補充を行うといった役割分担が考えられています。また、コンビニなどでの飲料補充のように、ロボットが裏で商品を逐次補充することも可能です。
こうした機械化・自動化によって対物業務が減少することで、将来的には人が本来業務である顧客とのコミュニケーションの時間が増えると考えられています。
【2】シニアの“ちょこっと仕事”
- ドラッグストアでの品出し
- 無理のないペースで社会とつながる働き方

「未来予測2040 労働供給制約社会がやってくる」より
2.シニアの小さな仕事
高齢者が無理なく社会と繋がり、貢献できる小さな仕事も、労働供給制約緩和に貢献する可能性があります。
高齢期の仕事や活動の例として、ドラッグストアの品出しが挙げられています。これは、無理なくできる範囲で世の中に貢献する姿として期待されています。
💡 消費者も“ちょっと労働者”?


最近のセルフレジ、私たちも一部「店員さんの仕事」をしてますよね。

「便利な消費」は、ちょっとした参加の上に成り立っているかも。
「未来予測2040 労働供給制約社会がやってくる」より
3.消費者の役割
労働供給制約社会では、消費者がサービス供給の担い手となるシチュエーションが増加します。
小売店のセルフ会計は、消費者が「セルフサービス」という形で労働供給を求められている例です。
✅ 最後に:未来をつくるのは、あなたの行動


技術も、人の力も、そして“わたし”も。みんなで支える未来へ。

「いらっしゃいませ」が残るお店を、これからも一緒に守っていきましょう!
「未来予測2040 労働供給制約社会がやってくる」より
まとめ
企業への過剰なサービス要求は、人手不足による代替要員の確保困難を招き、最終的に店舗の閉鎖や利便性の低下、価格上昇といった形で消費者に跳ね返ってくる可能性があるため、消費者は単なる消費者ではいられなくなるという認識が必要とされています。
これらの解決策(機械化・自動化ど)を全体として推進した場合でも、2032年以降には労働供給量が不足することが回避し難いことも示唆されています。
このように、商品販売分野は深刻な人手不足に直面しますが、機械化・自動化や多様な担い手の活用、そして消費者の協力によって、サービスの維持や働き方の変化が模索されると考えられます。
記事の執筆者のご紹介
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。

ホームページの各記事や事務所サービスのご案内
よく読まれている人気の記事(カテゴリー別)
- 社会福祉法人・企業主導型保育事業の質問と回答はこちら
- 社会福祉法人の役員(理事・監事)と評議員に関する手続き・監査指摘事項への対応はこちら
- 社会福祉法人会計で用いる勘定科目を科目ごとに分かりやすく解説はこちら
- 企業主導型保育事業の専門的財務監査の評価基準の解説はこちら
- 有料動画で学ぶ福祉の会計や経営はこちら
マツオカ会計事務所作成の書籍・動画・規程
20年間の社会福祉法人・福祉事業者の支援と、11年間の地方公務員の行政事務で培ったノウハウを 書籍・動画・規程 として公開しています。
ご自身で学び、法人内で活かせるコンテンツをご用意していますので、ぜひご覧ください。
▶ マツオカ会計事務所が提供する書籍・動画・規程まとめページを見る
出版中の書籍
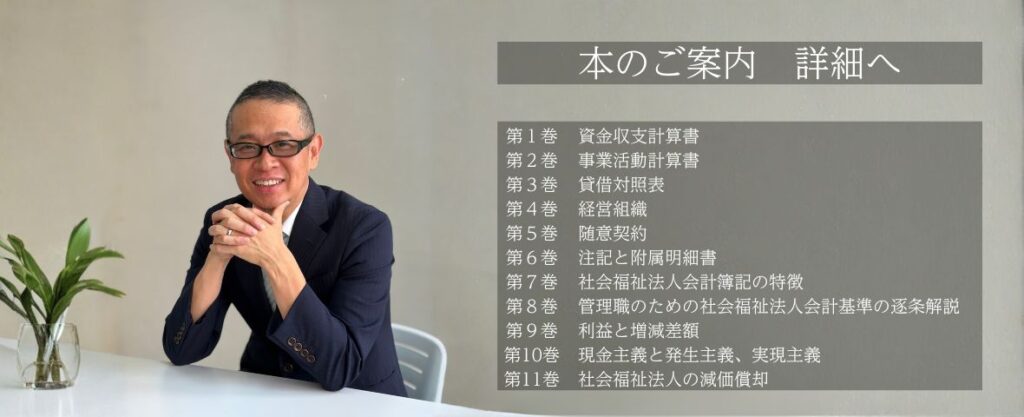
よかった。ありがとう。読んだ人が幸せでありますように。