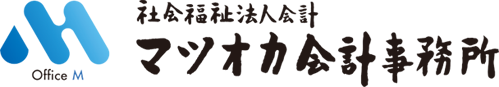会計と共に考える就労継続支援B型の制度と現場のいま
長くB型を運営されてきた法人の皆さまへ。制度の成り立ちをふまえて、これからの一歩を一緒に考えます。
「昔ながらのやり方が通じない」時代のなかで、
それでも地域に必要とされ続けるB型事業であるために。
就労継続支援B型は、長年にわたり障害のある方々の「働く」機会を支えてきた制度です。
しかし、近年では株式会社などの新規参入が進み、
利用者確保や運営の見直しを迫られる場面が増えてきました。
このページでは、制度の成り立ちを振り返りながら、
「なぜいま悩むのか」「どうすれば乗り越えられるのか」を考えるための情報をお届けします。
就労継続支援B型ができた背景
就労継続支援B型の制度は、一気に整ったものではありません。戦後から続いてきた「働く場」の模索と、現場の声を反映した制度化の流れの中で、少しずつ形になってきました。
戦後〜1980年代:制度の外で続いてきた「作業所」
- 知的障害や精神障害のある人にとって、社会とのつながりの場は「授産施設」や「小規模作業所」が中心でした。
- 法的な根拠がなく、民間の親の会などが自主運営するケースが多く、国の支援は不十分でした。
- 作業内容も内職や軽作業が多く、「労働」としての位置づけは弱いものでした。
1990年代:制度化を求める声の高まり
- 小規模作業所の数が増え、制度化の必要性が全国的に議論されました。
- 1993年には「小規模作業所調査研究事業」がスタートし、制度整備の第一歩が始まりました。
2003年:支援費制度のスタート
- 「小規模通所授産施設」などが初めて法的に位置づけられ、サービスの枠組みが整い始めました。
- ただし、まだA型/B型のような区分はありませんでした。
2006年:障害者自立支援法によりA型・B型が誕生
- はじめて「就労継続支援A型・B型」が制度として登場しました。
- A型=雇用契約あり、B型=雇用契約なし、という枠組みがこの時からスタートしました。
2013年:障害者総合支援法に移行
- 自立支援法の課題をふまえ、本人中心の柔軟な支援制度へと移行しました。
- B型は現在も総合支援法の枠内で位置づけられています。
制度の変遷まとめ
| 時代 | 出来事 | ポイント |
|---|---|---|
| 〜1980年代 | 小規模作業所・授産施設 | 制度の枠外での自主運営 |
| 1990年代 | 制度化の声が高まる | 調査研究事業スタート |
| 2003年 | 支援費制度 | 初の法的な位置づけ |
| 2006年 | 障害者自立支援法 | A型・B型が誕生 |
| 2013年〜 | 総合支援法 | B型制度の現在の枠組み |
就労継続支援A型とB型の違い
| 比較項目 | A型 | B型 |
|---|---|---|
| 雇用契約 | あり(労働者) | なし(通所者) |
| 報酬 | 最低賃金以上の賃金 | 工賃(成果に応じた報酬) |
| 主な対象者 | 安定して働ける力のある人 | 雇用は難しいが働く力のある人 |
| 利用期間 | 原則2年(延長あり) | 期限なし |
就労継続支援B型の特徴
- 雇用契約は結ばず、通所という形で働く機会を提供します。
- 作業内容は内職・軽作業・農作業・製菓・パン工房・喫茶運営など多様です。
- 生活支援や対人支援も含み、生活リズムの安定や社会参加を重視します。
- 週1日からの通所も可能で、柔軟に支援が受けられます。
利用者像(例)
- 障害の特性や体調から、一般就労や雇用契約が難しい方
- 生活のリズムを整えたい方、人と関わる機会を持ちたい方
- 経済的に自立したい方、年金以外の収入が必要な方
- 20代〜60代以上まで、さまざまな年齢の方が対象