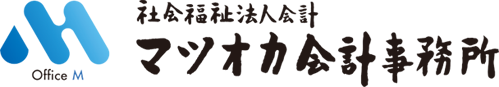社会福祉法人会計基準とパブリックコメント|厚労省の見解と通知の背景にせまる
通知文の裏にある行政の意図を、制度運用の根拠として読み解く
見逃されがちな制度の核心。
パブリックコメントにこそ、厚生労働省の本音がにじみ出る。
社会福祉法人会計基準に対して、国民や関係者の意見を募った「パブリックコメント」。
その回答には、厚生労働省の考え方や制度運用の背景が明確に記されています。
実務で判断に迷ったとき、「通知文」だけでなく「このページ」に立ち返ることで、根拠ある対応が可能になります。
▶︎ 会計基準・通知一覧ページに戻る
▶︎ 4コマで読む社会福祉法人会計基準(条文別まとめ)
社会福祉法人会計基準のパブリックコメント
(参考)項目名の説明
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| NO. | 厚生労働省のパブリックコメントに付与された番号 |
| 意見 | 一般からの意見や質問 |
| 回答(考え方) | 厚生労働省の回答や考え方(重要) |
移行期間
| NO. | 意見 | 回答(考え方) |
|---|---|---|
| 1 | 新会計基準への移行は、平成25年(予算時)から全ての法人において移行することとされておりますが、障害者福祉や児童福祉の制度改革が検討されている中で、混乱を回避するためにも移行期間の延長が必要と考えます。円滑な移行をするためには、移行期間の延長をお願いします。 | ご意見を踏まえ、移行期限を25年4月から27年4月に延長します。 |
1年基準
| NO. | 意見 | 回答(考え方) |
|---|---|---|
| 2 | 1年基準(ワン・イヤー・ルール)等の新たな会計手法について、小規模な社会福祉法人に導入するのは会計事務手続上無理があるのではないか。 | 社会福祉法人は公益性の高い法人であることから、1年基準等の新たな会計手法を導入することにより、事業活動の透明性を高め、利用者等に対し、経営実態をより正確に反映した情報を提供する必要があると考えています。 なお、これらの会計手法には簡便法を多く取り入れており、会計実務の負担にも一定の配慮をしています。 |
| 3 | 新会計基準では、いわゆるワンイヤールールが適用されている。 しかしながら、5年掛捨ての前払火災保険料等、少額なものまで厳格にワンイヤールールを求めることは、事務の煩雑性を招くので、重要性の乏しいものについては、資金の範囲として会計処理を認めていただきたい。 | 重要性の原則は全ての会計処理に適用されますので、法人の規模等に応じてご判断ください。 |
勘定科目
| NO. | 意見 | 回答(考え方) |
|---|---|---|
| 4 | 資金収支計算書と事業活動計算書では同じ勘定科目名が使用できるようにしてほしい。 | 資金収支と損益は概念が違うため、別々の勘定科目としています。 |
| 5 | 社会福祉協議会に関する勘定科目について、大区分勘定科目として新設されている「社会福祉協議会事業収入」「社会福祉協議会事業収益」の科目名について、「社会福祉協議会」は社会福祉事業をはじめとする社会福祉を目的とする様々な事業を行っている組織の呼称であり、「社会福祉協議会事業」という事業があるわけではない。したがって、今回の案における「社会福祉協議会事業収入(収益)」とする科目名が設定された場合、社会福祉協議会が行うあらゆる事業が当てはまり得ることから、当該科目が適切に利用されないことや、情報公開に当たり正しく理解されない恐れがある。 | 「社会福祉協議会収入(収益)」を削除し、「○○収入」を追加しますので、それを使用してください。 |
| 6 | 割賦取引による固定資産の購入の場合、貸借対照表上、「<固定負債>長期未払金」を計上することになるが、当該「長期未払金」の計上に伴う資金収支計算書上の勘定科目が設定されていないのはなぜか。 | ご指摘の事例の場合、支払資金に変動がありませんので、資金収支計算書に計上は不要です。これは従来と同様の考え方です。 |
| 7 | 資金収支計算書中「<中区分>その他の事業収入<小区分>補助金事業収入」とありますが、助成金が多い昨今を鑑みて「補助金事業収入」だけではなく「補助金等事業収入」とすべきではないでしょうか。助成金についてはどの勘定科目に計上すべきでしょうか。 | ご指摘を踏まえ、「(中区分)その他の事業収入(小区分)補助金事業収入」の勘定科目説明に「助成金」を追加します。 |
| 8 | 運用指針Ⅰ-12におけるサービス区分間の貸付金(借入金)と貸借対照表との関係はどのように考えればよいか。特に拠点区分貸借対照表において、これらの科目は表示されるのか。 | サービス区分間貸付金(借入金)明細書は年度末にサービス区分間の貸付残高が残っていないかを確認するための明細書であり、拠点区分貸借対照表に表示されることはありません。 |
| 9 | 会計基準(注7)において、「長期借入金の担保に供している預貯金は、固定資産に属するものとする。ただし、当該目的を示す適当な科目で表示するものとする」としているのはなぜか。 | 長期借入金の担保であり流動性はないことから固定資産になります。科目は内容がわかる名称としてください。 |
| 10 | ・1年以内に返済期日が到来するものについては、新会計基準では固定負債の部から、流動負債の部の各科目へ振替えるとのことですが、この場合、この際、資金収支計算書の勘定科目についてはどの科目を使用すればよいのか。 | ・会計基準(注6)にあるとおり、1年基準による固定資産(負債)から流動資産(負債)への振り替えは支払資金には影響しませんので資金収支計算書への記載は不要です。 |
| 11 | ・「事業区分間長期借入金」「拠点区分間長期借入金」については、その他の活動による支出の中に、「事業区分間長期借入金返済支出」「拠点区分間長期借入金返済支出」の科目があるようですが、科目説明の中には1年以内の償還額を含むと記載されていません。 | ・ご指摘のとおり、「事業区分間長期借入金返済支出」「拠点区分間長期借入金返済支出」の科目説明の中に1年以内の償還額を含む旨を追加しました。 |
| 12 | 勘定科目について、現行「社会福祉法人会計基準」の措置費収入のうち事業費収入が新しい会計基準では記載されていません。 第1号の1様式に「小区分については適当な科目を追加できるものとする」と記載されていますが、大区分(生活保護事業収入)、中区分(措置費収入)、小区分(事業費収入)の次に小区分(事務費収入)を記載した方がよいのではないでしょうか。 | ご指摘を踏まえ、生活保護事業収入の措置費収入の中に、小区分として「事業費収入」を追加します。 |
| 13 | 資金収支計算書と貸借対照表科目の整合性を図るため、貸借対照表科目のうち、資金収支科目でもあるものはその旨の表示をしていただきたい。 | 支払資金の範囲は、基本的に流動資産から流動負債をマイナスしたものであり、範囲が限られているため不要と考えています。 |
| 14 | 資金収支計算書の「事業活動支出」のうち「(大区分)事業費支出/(中区分)管理費返還支出」について、事業活動計算書には無いのはなぜか。 | 仕訳上、「長期預り金(資産)/現金(資産)」となるので、事業活動計算書にはこの勘定科目は出てきません。 |
| 15 | 勘定科目説明(案)において、 ・事業活動計算書「(大区分)老人福祉事業収益/(中区分)運営事業収益/(小区分)管理費収益」 ・事業活動計算書「(大区分)老人福祉事業収益/(中区分)その他の事業収益/(小区分)管理費収益」上記の科目については、一括徴収分の償却額を含む旨の説明が必要ではないか。 | ご指摘のとおり、「一括徴収分の償却額を含む」旨を追加します。 |
| 16 | 勘定科目説明(案)において、 資金収支計算書「(大区分)事業費支出/(中区分)管理費返還支出」 上記の科目は、長期預り金の返還を含むのか。この場合、多額の金額が計上されることもあり得るが、差し支えないか。 | 長期預り金の返還を含みます。多額の金額が計上されることも考えられます。 |
| 17 | 勘定科目説明(案)において、 貸借対照表「(大区分)固定負債/(中区分)長期預り金」 上記の科目を収入した場合に、これに対応する資金収支計算書に計上する科目を設けるべきではないか。 | 資金収支計算書上、「(大区分)老人福祉事業収入(中区分)運営事業収入(小区分)管理費収入」、「(大区分)事業費支出(中区分)管理費返還支出」になります。 |
| 18 | 勘定科目の(大区分)事務費に「保険料」がありますが、利用者を対象とした保険に加入して事業者が支払う場合には保険料であっても事業費で処理を行うべきケースが多々生じております。従って、事業費としての「保険料」の勘定科目が必要と判断いたします。 | ご指摘のとおり、事業費にも「保険料」を追加します。 |
| 19 | 救護施設は、昭和32年3月30日社発第254号、各都道府県知事、指定都市市長宛厚生省社会局長通知。最終改正平成13年3月27日社援発第520号「生活保護法による保護施設の管理規程について」の第19より第23において作業に関する定めがあります。とりわけ、第23におい て、「入所者に作業を課した場合において生じた収益(作業に要した必要経費を除く。)の処分については、原則として入所者の処遇にあてるように規定することが適当であること。」とされています。 この規程を根拠として多くの救護施設が施設内外の資源を利用して利用者支援のための作業を実施しています。 2 今回の基準案に関する疑義 (1)この作業により得た収入は、基準案資料4勘定科目説明(以下の疑義についても同じ。)の資金収支においては、雑収入の小区分として必要な勘定科目を設定し、事業活動計算においては、その他の収益の中区分・小区分として必要な勘定科目を設定し処理するものと理解してよろしいでしょうか。 | 資金収支計算書の「<大区分>生活保護事業収入<中区分>その他の事業収入<小区分>その他の事業収入」並びに事業活動計算書の「<大区分>生活保護事業収益<中区分>その他の事業収益<小区分>その他の事業収益」で処理してください。 |
| 20 | (2)この作業の継続のために必要な経費は、事業費若しくは事務費の該当支出科目において処理を行うのか、若しくは、通知の趣旨を厳密に解釈し、収支の透明性を図るため資金収支のその他の支出の雑支出並びに事業活動のその他の費用に中区分・小区分として必要な勘定科目を設定して処理するのかご教示いただきたい。 | 資金収支計算書の「<大区分>事業費支出<中区分>雑支出」並びに事業活動計算書の「<大区分>事業費<中区分>雑費」で処理してください。 |
| 21 | (3)上記の結果の収支差額については、利用者の作業金として現金による還元ならびに事業費等への還元を行うことによって、通知にある「原則として入所者の処遇にあてる。」方法を取ることが至当と考えますが、この場合の処理は、以下のとおりの方法が考えられますがどのように判断すべきかご教示いただきたい。 ① 作業金として現金による還元を行う場合 資金収支のその他の支出の雑支出ならびに事業活動のその他の費用に中区分・小区分として必要な勘定科目を設定して処理する方法でよろしいか。 ② その他の方法により利用者処遇に還元した場合は、当該計算書の該当勘定科目にて処理すれば良いのか、資金収支のその他の支出の雑支出ならびに事業活動のその他の費用に中区分・小区分として必要な勘定科目を設定して処理するのかご教示いただきたい。 | ①、②とも、資金収支計算書の「<大区分>事業費支出<中区分>雑支出」並びに事業活動計算書の「<大区分>事業費<中区分>雑費」で処理して下さい。 |
| 22 | (4)その他以下のケースにおいては、どのような処理をすべきかご教示いただきたい。 ① 作業を実施していてもまったく収入の無い場合、必要経費は事務費ならびに事業費の当該勘定科目にて処理すると理解してよいでしょう か。 ② 区市町村、町会、近隣企業等との委託契約(例:花壇整備、定期清掃等)による収入が発生した場合は、資金収支の「その他の事業収入」による処理若しくは「雑収入」のどちらでしょうか。事業活動については、資金収支の判断に基づくとしてよいでしょうか。 | ①の場合については、資金収支計算書の「<大区分>事業費支出<中区分>雑支出」並びに事業活動計算書の「<大区分>事業費<中区分>雑費」で処理して下さい。 ②については、資金収支計算書の「<大区分>生活保護事業収入<中区分>その他の事業収入<小区分>その他の事業収入」並びに事業活動計算書の「<大区分>生活保護事業収益<中区分>その他の事業収益<小区分>その他の事業収益」で処理してください。 |
| 23 | 「勘定科目設定」について 1 生活保護事業収入に関する勘定科目設定について 資料4勘定科目説明の生活保護事業収入、措置費収入、事務費収入については、案のとおりと考えていますが、従来ありました事業費収入と利用者負担金収入はどのように処理をすることになるのでしょうか。以下の点についてご教示いただきたいので、よろしくお願いします。 (1)事業費収入について 従来事業費として処理されてきたものは、毎年厚生労働省告示別表第1-第1章-2救護施設等基準生活費ならびに別表第1-第2章-2障害加算により定められ、利用者の入所状況により福祉事務所より各救護施設等に支払われているものです。 また、従前事務費と事業費については、その支出内容や措置費の弾力運用等に条件が定められており、経理処理にあたっては事務費・事業費を確定した根拠を明確にしておくことが求められてきました。このことは、事務費も含めて公費による収入であることから当然のことといえます。 (2)利用者負担金収入について さらに、厚生労働省事務次官通知として、福祉事務所による収入の認定が行われる仕組みになっています。具体的に入所者にとっては、障害基礎年金や家族からの援助等が収入認定の対象となります。 この場合、従前は、(大区分)利用料収入(中区分)利用者負担金収入(小区分)事務費負担金収入若しくは事業費負担金収入として処理し、上記事務費収入や事業費収入と併せて当該年度に受領する | ご指摘のとおり、 (1)生活保護事業収入の措置費収入の中に、小区分として「事業費収入」を追加します。 (2)生活保護事業収入の中に、「利用者負担金収入」を追加します。 |
| 24 | 勘定科目説明のうち、「○○取得支出」等については、必要に応じた勘定科目として設定すれば良いと解釈してよいでしょうか。 | 必要に応じて勘定科目を設定してください。 |
| 25 | 会計基準(注8)において、「光熱水費」とあるが、勘定科目説明では、「水道光熱費」となっているのはなぜか。 | ご指摘を踏まえ、「水道光熱費」に修正します。 |
| 26 | 会計基準(注14)において、「当期の、為替差損益として処理する」とあるが、勘定科目説明に当該科目がない。 | 資金収支計算書では「流動資産評価益等による資金増加額(減少額)」の中区分として「為替差益(差損)」を、事業活動計算書では「その他のサービス活動外収益(費用)」の中区分として「為替差益(差損)」を追加しました。 |
| 27 | 運用指針Ⅰの9-(1)(3)について「設備整備等寄付金収入」とあるが、勘定科目説明では施設整備等寄付金収入となっている。 | ご指摘の通り「施設整備等寄附金収入」と修正します。 |
| 28 | 資金収支計算書では「(大区分) 設備資金借入金元金償還補助金収入」となっているが、事業活動計算書では「(中区分)設備資金借入金元金償還補助金収益となっている。 | ご指摘の通り、「(中区分)設備資金借入金元金償還補助金収入」と修正します。 |
| 29 | 勘定科目説明中、「授産事業支出」の中区分として「○○事業支出」の記載がない。 | ご指摘のとおり、資金収支計算書の勘定科目に「○○事業支出」を追加します。 |
| 30 | 勘定科目説明中、「授産事業費用」に中区分として「○○事業費」の記載がない。 | ご指摘のとおり、事業活動計算書の勘定科目説明に「○○事業費」を追加します。 |
| 31 | 科目の分類 勘定科目説明 小区分「受託事業収入」の備考について、「受託事業に係る利用者からの収入も含む」と記されているが、放課後児童健全育成事業(学童保育)における保護者から集金された施設利用料は「私的契約利用料収入」と「受託事業収入」のどちらで処理すべきか。また教材費についはどうか。 | 「私的契約利用料収入」は、私的契約に基づいて保育所に入所している場合の利用料収入を計上する勘定科目です。従いまして、放課後児童健全育成事業の実施形態が補助事業か委託事業かに応じて、「補助金事業収入」又は「受託事業収入」に計上して下さい。教材費については、通常は補助でも委託でもないので「その他の事業収入」となります。ただし、補助事業に係る教材費であれば「補助金事業収入」、受託事業にかかる教材費であれば「受託事業収入」となります。 |
| 32 | 「勘定科目説明」中、「(大区分)事務費支出(中区分)事務消耗品費支出」について、「事務用に必要な器具什器のうち、固定資産の購入に該当しないものの支出をいう。」と記されているだけだが、事務用の消耗品の処理科目もこの科目でよいか。 | ご指摘のとおり、「事務用に必要な消耗品及び器具什器のうち~」と修正します。 |
| 33 | 勘定科目説明中、「(大区分)事務費支出(中区分)保険料支出」について、「ただし、福利厚生費、器機設備保険料に該当するものは除く。」とあるが、具体的にどのような内容のものか。 | 福利厚生については、社員向けの福利厚生行事等に関する保険料支出を想定しています。なお、「器機設備保険料」は削除します。 |
| 34 | 勘定科目中、事業活動計算書の「(大区分)固定資産移管収益・費用」がどのような取引で使用すべき科目か不明なので、運用指針で記載すべきである。 | 「勘定科目説明」に記載してあるとおり、拠点区分間又は事業区分間の固定資産の移管があった場合に使用する科目です。 |
| 35 | 新たに「未収補助金」の科目が設定されたが、施設整備等の補助金は複数年度にまたがって支払われることも多いことを踏まえると、どの時点で計上すべきか一定の基準が必要であり、このことを運用指針で明記すべきである。 | 補助金の補助事業年度に合わせて計上してください。 |
| 36 | 会計基準(注11)における償還補助相当の補助金の国庫補助金等特別積立金への積立は、どの勘定科目を使えばよいのか。 | 事業活動計算書における「(大区分)国庫補助金等特別積立金積立額」を使用してください。 |
| 37 | 資金収支計算書の中の施設整備等による収支に新たに設けられた「その他の施設整備等による支出」についてですが、その具体的な内容を事例を提示して、「勘定科目説明」又は「運用指針Ⅰ」に記載していただけないでしょうか。 | 柔軟な処理を可能にするため、明示されている勘定科目以外の施設整備等による経費が生じた場合の勘定科目として設定しているものです。 |
| 38 | 共同募金会・社会福祉協議会への適用 収入及び支出とも独特の科目名を使用して事業を実施しており、基準上の科目では対応できないのではないか。 | 基準上明示していない勘定科目がある場合には、○○収入(支出)、○○収益(費用)等の科目で対応することが可能です。 |
| 39 | 勘定科目説明(案)の3「貸借対照表目の説明」によれば、流動資産に掲げられている有価証券の例示として、国債・地方債などが例示されている。通常、国債・地方債などは長期保有を目的としている。これらは固定資産に例示すべきではないか。 | 国債・地方債も短期売買する可能性があるので、流動資産の例示としています。 |
| 40 | 資金収支計算書では当年度支払額全額を「職員賞与支出」で処理するのに対し、事業活動計算書では、支払額の内当年度対応分を「職員賞 与」、前年度対応分は「賞与引当金」を取り崩して支払うことになります。この場合、「職員賞与支出」と「職員賞与」の額が異なりわかりにくいものになってしまうのではないか。 | 「支出」は支出のあった年度に全額計上されますが、「費用」は発生した年度に計上されますので、相違することがあると考えています。 |
| 41 | 会計基準「第2号の1様式」から「第2号の4様式」まで、国庫補助金等特別積立金取崩額には科目名称の先頭に「△」が記されていますが、実際の決算書にも「△」を記す必要があるのか。 | ご指摘のとおり、科目名から「△」を削除し、金額欄に「△」を追加します。 |
| 42 | 会計基準「第1号の1様式」の冒頭の注意書きについて、「水道光熱費、燃料費、賃借料」について弾力運用保育所において、事業費と事務費に分けて計上することはできないのか。 | 弾力運用が適用されるケースでは、「水道光熱費」等を事務費、事業費に厳密に分ける必要はないため、原則として事業費に一括して計上することとしたものですが、必要に応じて、事業費と事務費に分けて計上していただいてもかまいません。 |
簡素化
| NO. | 意見 | 回答(考え方) |
|---|---|---|
| 43 | 減価償却費の配分について、サービス区分ごとの配分は行わなくて良い特例を設けて欲しい。 | 運用指針13において、別添1の配分方法によりがたい場合は、実態に即した合理的な配分方法によることを認めています。 |
| 44 | 共通経費の配分や1年基準を厳密に行うことは事務負担を増大させることになるので、金額が少額なものや、経営管理上配分の意味が薄いものについては、事業所判断で「重要性の乏しいもの」としての簡便化処理が出来るようにしてほしい。 | 重要性の原則について、法人の規模等に応じて、法人で重要性の判断を行うものと考えています。なお、所轄庁の指導がある場合には、それに従ってください。 |
| 45 | 給食用材料の計上について、現実的に給食用材料の棚卸は大変な手間を伴い困難ではないかと思う。また実際に多くはすぐに消費するものではないか。資産としての価値も低い。重要性に乏しく、計上しない選択もできるようにして欲しい。 | 重要性の原則は全ての取り引きに適用されますので、実態に即してご判断いただいて結構です。 |
関連当事者
| NO. | 意見 | 回答(考え方) |
|---|---|---|
| 46 | 会計基準(注22)1における「役員」の定義を明らかにして欲しい。理事、監事だけなのか、それとも法人規程による執行役員なども含まれるのか。 | 理事及び監事を想定しています。 関連して、運用指針22-(1)「関連当事者の範囲」において、「(準ずる者を含む。)」を削除します。 |
寄附金
| NO. | 意見 | 回答(考え方) |
|---|---|---|
| 47 | 運用指針Ⅰ-9-(2)において「土地などの支払資金の増減に影響しない寄附物品については、事業活動計算書の固定資産受増額として計上するものとし、資金収支計算書には計上しないものとする。」と規定しているところであるが、当該会計処理に則った場合、「資金収支予算書」に当該取引が反映されない結果となるのではないか。 | 固定資産で支払資金の増減に影響しないものは資金収支計算書に計上する必要はありません。必要に応じて、予算書上に寄附金収入の額を明示していただくことは可能です。 |
| 48 | 運用指針Ⅰ-9-(3)寄附金の扱いについて、「共同募金会からの受配者指定寄附金については、主として設備整備等寄附金収入として計上し、併せて設備整備等寄附金収益として計上する。」とあるが、「施設整備等寄附金収入・施設整備等寄附金収益」ではないか。 | ご指摘のとおり、「施設整備等寄附金収入」「施設整備等寄附金収益」に修正します。 |
| 49 | 運用指針Ⅰの9-(2)寄附金の扱いについて「土地などの支払資金の増減に影響しない寄附物品については、事業活動計算書の固定資産受贈額として計上するものとし、資金収支計算書には計上しないものとする。」とありますが、「土地など」の「など」の定義を明らかにしてほしい。 | 建物など支払資金の増減に影響しない土地以外の固定資産です。 |
基本金
| NO. | 意見 | 回答(考え方) |
|---|---|---|
| 50 | 4号基本金は、決算上の繰越金を生じた場合に定款準則第18条第3項の規定により発生する会計処理ですが、新会計基準策定に際し定款準則の変更は予定されていないと認識しております。このことから、法人の経営努力によって生じた当期繰越金を定款に基づき適正に処理するものとして、4号基本金を残すべきと考えます。 また、第4号基本金が廃止の場合には新会計基準へ移行する際にその全額を取崩し、事業活動収支計算書の繰越活動増減差額に基本金取崩額(第4号基本金取崩額)として計上され、結果として次期繰越活動収支差額が増えることになると認識しますが、一般の方からみれば、移行時の年度に多額の収入があったものとして捉えられ誤解を生む一因となる恐れがあるので、廃止については改めて頂くべきと考えます。 | 基本金を法人の設立及び施設整備等、法人が事業活動を維持するための基盤として収受した寄附金に限定し、事業活動の結果として収支差額を振り替える現行基準の4号基本金は、他の基本金は、他の基本金と性格が異なるため、廃止することとしました。 なお、定款準則第18条により、基本財産に組み入れた場合においても、基本金に組み入れる必要はありません。 また、法人が任意で4号基本金相当額の積立金を積立ることは可能です。 なお、移行時の特例として、4号基本金の取崩額を事業活動収支計算書の繰越活動増減差額の部に計上する方法に代えて、貸借対照表上、直接「次期繰越活動増減差額」又は「○○積立金」に組み替えることを可とします。 |
| 51 | 基本財産の土地・建物も当然ながら減損会計の対象となるが、例えば基本財産の土地を減損処理した場合、これに対応する基本金はどうするのか。 | 基本金は減価償却にも対応していませんので、減損にも対応しません。 |
| 52 | 運用指針Ⅰ-14-(3)「基本金を取り崩す場合には、基本財産の取崩しと同様、事前に所轄庁に協議し、内容の審査を受けなければならない」のはなぜか。 | 「社会福祉法人の認可について(平成12年12月1日厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知)」別紙1「社会福祉法人審査基準」第2の2(1)において「基本財産を処分する場合には所轄庁の承認を受けなければならない」としているためです。 |
| 53 | 4号基本金が廃止された事に伴い、基本財産に計上されている「基本財産特定預金」はどのような扱いになるか指導願いたい。 | 4号基本金の廃止にあわせて、基本財産特定預金を処分する必要はありません。 |
共通経費
| NO. | 意見 | 回答(考え方) |
|---|---|---|
| 54 | 1つの「拠点区分(事業所)」で複数の事業を実施している場合、どうしても経費を「按分」をせざるを得ない状況にあります。「水道光熱費」や「人件費」は按分の根拠を定めるのが非常に難しいため、流動的に行えるようにしていただきたい。 | 按分については運用指針別添1に配分方法を例示しており、またそれ以外の方法も認めていますので、実態に合致したものを使用してください。 |
| 55 | 運用指針Ⅰ-13-(2)について、水道光熱費、燃料費、賃借料は、原則として事業費とされているが、本部に係る経費は事務費ではないか。 | 「原則」として事業費としていますが、実情に応じて事務費に計上していただくことも可とします。 |
共同募金
| NO. | 意見 | 回答(考え方) |
|---|---|---|
| 56 | 運用指針Ⅰ-9-(3)「共同募金会からの受配者指定寄付金については、主として施設整備等寄付金収入として計上し、・・・」とあるが、「主として」とはどのような趣旨か。 | 「主として」は削除し、施設整備及び設備整備に係る配分金と経常的経費に係る配分金の処理方法を明確にしました。 |
| 57 | 拠点区分について、共同募金会は、県内各市町村単位に支分会があり、それぞれを拠点区分として適用することは、過重な事務となるのではないか。 | 共同募金会の市町村の支分会は都道府県共同募金会と一体的に運営されているため、同一の拠点区分としていただいてかまいません。 |
| 58 | 運用指針Ⅰ-9-(3)「また、施設整備事業及び設備整備事業にかかる配分金は資金収支計算書の施設整備等補助金収入及び事業活動計算書の施設整備等補助金収益に計上し、国庫補助金等特別積立金を積み立てることとする。」と運用指針Ⅰ-15-(1)「なお、施設の改修や固定資産の習得の目的で共同募金会から受け取る特別配分金を国庫補助金等に含むものとする。」が同じことを指しているのであれば、表現を統一すべきではないか。また、特別配分金の定義が不明確である。 | ご指摘のとおり、「施設整備及び設備整備に係る配分金」に統一しました。また、「特別配分金」は「受配者指定寄附金以外の配分金」に修正しました。 |
拠点区分
| NO. | 意見 | 回答(考え方) |
|---|---|---|
| 59 | 拠点区分はなぜ設定するのでしょうか。その必要性を教えてください | 現行の会計基準では、施設、事業所単位での財務状況が把握できないという問題がありましたが、拠点区分を設けることにより、施設、事業所単位での、実態に即した運営管理が可能になると考えています。 |
| 60 | 多岐に亘る事業を行っている法人にとっては拠点区分の仕方が分かりづらい。所在地が点在してい る場合や、同一敷地内で異種事業を行っている場合などもある。拠点をどのように分けるのか、詳細を示してほしい。 | 拠点区分は、一体として運営される施設、事業所又は事務所をもって1つの拠点区分とします。具体的な区分については、法令上の事業種別、事業内容及び実施する事業の会計管理の実態を勘案して設定します。所在地が点在していても、共通経費等を一体的に管理している等、一体的な運営管理がなされていると判断できる場合等には、同一拠点とすることができます。 |
| 61 | 拠点区分の方法を明確にして欲しい。 | 運用指針4において、拠点区分の原則的な方法を記載しています。 |
| 62 | 拠点区分の設定に当たり、例えば、保育所経営を行う一方、介護保険法に規定する通所介護事業所を併設する場合、拠点区分は「保育所」区分のみとし「通所介護事業所」をサービス区分とするのか、または、拠点区分を「保育所」及び「通所介護事業所」の2拠点とするのかが不明である。もし、いずれの拠点区分の設定も可とするならば、運用指針Ⅰ-5-(3)「サービス区分ごとの明細書の作成について」の規定によると、拠点区分を前者の「保育所」区分のみとした場合、介護保険サービスを実施しているのもかかわらず、「拠点区分事業活動明細書(別紙4)の作成は省略することができる。」という解釈になるが、当該解釈でよろしいか。 | 保育所と、介護保険法に規定する通所介護事業所とは法令上の事業種別が異なるため、独立した拠点区分とします。 |
| 63 | 会計基準(注3)では、「拠点区分は、原則として、予算管理の単位とし」とあるが、運用指針Ⅰ-6では、「年度内返済が行われていない場合は、本部会計を1つの拠点として・・・」とは、いつの時点をもって判断するのか。 | 運用指針6について、「年度内返済が行われていない場合は、「サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書を作成するものとする。」と修正します。 |
| 64 | 拠点区分はそもそも経営的判断に資するため、当該法人の合理的な基準によって、任意的に定めるべきであり、会計基準で強制的に行わせることは、いたずらに事務処理の煩雑をもたらし、経営的判断が不明瞭となる。よって、拠点区分については、法人の任意とすべきである。 | 現行の会計基準では、施設、事業所単位での財務状況が把握できないという問題がありましたが、拠点区分を設けることにより、施設、事業所単位での、実態に即した運営管理が可能になると考えています。 また、拠点区分は会計管理の実態に即して設定されるものでありますが、一定のルールも必要であると考え、運用指針において設定の原則的な方法をお示ししたものです。 |
| 65 | 社会福祉協議会においては、区域(市町村)内に同一の事業を複数の拠点で実施している例が多くあるため、市町村社会福祉協議会を一つの拠点区分としたい。 | 運用指針4に定めたとおり、法令上の事業種別を勘案した上で、一体として運営される施設、事業所又は事務所をもって一つの拠点区分としてください。 |
| 66 | 社会福祉法人が1つの保育所のみを経営し、その保育所が保育サービスのみを実施している事となるケースにおいて、サービス区分の設定は必要となるのか。 | サービス区分は、拠点区分において複数の事業を実施する場合に設定しますので、保育サービスのみを実施している場合には、サービス区分の設定は必要ありません。ただし、当該拠点に本部が存在する場合には「本部」と「○○保育所」という様にサービス区分の設定等が必要になります。 |
減価償却
| NO. | 意見 | 回答(考え方) |
|---|---|---|
| 67 | 会計基準(注17)(1)について、減価償却の対象を「1個若しくは1組の金額10万円以上の有形固定資産及び無形固定資産」としていますが、従来病院会計準則準拠の施設では20万円以上で行っており、10万円以上とすると、対象が余りにも拡大し、作業負担が過大となることが想定されま す。 | 注解から「10万円以上」という規定を削除し、運用指針17において、「原則として1個若しくは1組の金額が10万円以上」と修正しました。 |
| 68 | 会計基準.(注7)について、「減価償却の方法としては、建物等の有形固定資産については、定額法又は定率法のいずれかの方法で償却計算も行う」とあるが、建物にも定率法による減価償却を許容するのか。 | 定率法を認めないわけではありませんが、「減価償却の方法としては、有形固定資産については、定額法又は定率法のいずれかの方法で償却計算を行う。」に修正します。 |
| 69 | 会計基準(注25)について、「なお、有形固定資産及び無形固定資産以外に減価償却資産がある場合には、当該資産についても記載するものとする。」とあるが、どのような資産を想定しているのか。 | 長期前払費用を想定しています。 |
| 70 | 運用指針Ⅰ-17-(2)-ア「耐用年数到来期においても、使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価額(1円)まで償却を行うことができるものとする。」とあるが、備忘価額までの償却の具体的方法は、①税法を準用し5年で償却する。②それまでの償却方法を延長する。③金額が重要でなければ一括償却するの3通りが考えられるが、これらのいずれか? | 基本的には、それまでの償却方法の延長になります。 |
| 71 | 運用指針Ⅰ-17-(2)-イ「ただし、前項によって処理することもできる」とあるが、これが、残存価額を10%とする意であるとすると、何故そうなるのか根拠がよくわからない。残存価額10%が現在の経済実態と乖離しているからこそ改正があったのではないか | 「ただし書き」は削除しました。 |
減損会計
| NO. | 意見 | 回答(考え方) |
|---|---|---|
| 72 | 「減損会計の導入」について、使用価値の算定方法を明確にしていただきたい。 | 使用価値の算定方法等については、公認会計士協会による実務指針等を参考にしてください。 |
| 73 | 減損会計について、減損会計の対象となる固定資産を明確にして頂きたい。また、仮に施設の建物を減損処理の対象とするならば、建物取得時に国庫補助金を受配しているケースが多々ある。国庫補助金等特別積立金は減損処理するのか。 | 基本的に土地・建物を想定しています。また、ご質問のようなケースでは国庫補助金等特別積立金を評価減の割合に応じて取り崩します。 |
| 74 | 会計基準(注18)の「対価を伴う事業」の定義を明らかにして欲しい。また固定資産の減損会計は任意適用と考えて問題ないか。 | 社会福祉事業もすべて対価を伴う事業と考えておりますので、社会福祉事業、公益事業、収益事業すべてに適用可能です。原則として強制評価減を適用しますが、対価を伴う事業については、使用価値の見積もりによる減損会計の適用が可能となります。 |
減損会計、税効果会計
| NO. | 意見 | 回答(考え方) |
|---|---|---|
| 75 | ・減損会計・税効果会計基準は、事務処理が煩雑であり、社会福祉会計には不要ではないか。 | 減損会計は強制評価減に対する救済措置という意味合いを持つものですので、使用を強制するものではありません。税効果会計も税法上の収益事業に限定されるものです。 |
国庫補助金
| NO. | 意見 | 回答(考え方) |
|---|---|---|
| 76 | 国庫補助金等特別積立金の積立て及び取崩しについて、現行基準において、10万円未満の初期調度物品等を1号基本金及び国庫補助金等特別積立金から除外していたが、新基準では固定資産以外でも計上するように変更されたところである。その場合、固定資産以外で積み立てた国庫補助金等特別積立金の取崩は、その期に行われるが、その国庫補助金等特別積立金取崩額は、事業活動計算書の減価償却費の控除項目の国庫補助金等特別積立金取崩額に計上するのか? | 事業活動計算書の減価償却費の控除項目として計上してください。 関連して、会計基準第3章4(1)を「なお、サービス活動費用に減価償却費等の控除項目として~」と修正します。 |
| 77 | 会計基準(注11)では、「(1)施設及び設備の整備のために国及び地方公共団体等から受領した補助金、助成金及び交付金等を計上するものとする。」とあり、また、「運用指針Ⅰの14基本金について(1)ア」及び「運用指針Ⅰの15国庫補助金等特別積立金について(1)」でも固定資産以外も計上の対象になる旨が明示されていないため、明示すべきではないか。 また、国庫補助金等特別積立金を何故積立てるのかは、整備等の多額の補助金を一時の収益とするのではなく、期間収益として当該固定資産が費用化される期間にわたって認識することが会計上の目的と判断いたします。従って、即時消費される費用に対する補助金等の収益は翌期以降の収益とすべく繰り延べる必要はないので、国庫補助金等特別積立金の対象として積立てる必要はないものと判断いたします。 | 従来、国庫補助金等特別積立金の対象について、「(固定資産に限る)」としていたものを削除しましたので、固定資産以外も含まれることとなります。 国庫補助金等特別積立金の取扱いが旧基準と指導指針で異なっていたものを一元化したもので、国庫補助金の対象となったものを一旦積み立てることにしたものです。 |
| 78 | 運用指針Ⅰ-15において、借入金償還補助金の積立は受領会計年度とされているが、取崩しは償還補助予定額の総額を基礎とするということでよろしいでしょうか。 | 貴見のとおりです。 |
| 79 | 固定資産以外の物品について国庫補助金を受配した場合についても、国庫補助金積立計上するということでよろしいか。 | 固定資産以外も含めて国庫補助金の対象となったものをすべて計上することとなります。 |
| 80 | 運用指針Ⅰ-15-(1)にある「「社会福祉施設等施設整備費の国庫負担(補助)について」に定める施設整備事業に対する補助金など」の範囲は何か。 | 主として固定資産の取得に充てられることを目的として、国及び地方公共団体等から受領した補助金、助成金及び交付金等が該当します。 |
| 81 | 会計基準(注10)について、国庫補助金等特別積立金の取崩額は減価償却費に対応することとされており、減価償却の際の残存価額が10%なら国庫補助金等特別積立金も10%が残されると考えてよいか。また固定資産の備忘価額である1円は、国庫補助金等特別積立金においても残されることとなるのか。 | 貴見のとおりです。また、備忘価格である1円は国庫補助金等特別積立金に残す必要はありません。 |
| 82 | 会計基準(注10)について、国庫補助金等特別積立金に10%残す場合、これまで減価償却の残存価額を取得価額の10%とし、国庫補助金等特別積立金には残さないものとして計算していた場合、10%を残して算出した結果を移行年度期首に積み直すべきか。 | 重要性の乏しいもの以外は、「移行時の取扱い」に従い調整をお願いいたします。 |
| 83 | 償還補助金を該当固定資産へ按分し固定資産台帳へ記載する必要が生じると考えると、1ケの固定資産に対して、設備整備時の記載と償還補助時における記載の2行が必要と考えるが指導願いたい。 | 「基本財産及びその他の固定資産の明細書」(会計基準別紙1)の注1を参考としてください。 |
| 84 | 運用指針Ⅱ-2「旧基準からの移行の場合」(9)イ移行時の特例において、「①の方法」とは何を指すのか不明確である。 ※他基準、準則においても同様である。 | ご指摘のとおり「アの方法」と修正しました。 |
サービス区分
| NO. | 意見 | 回答(考え方) |
|---|---|---|
| 85 | 拠点において実施する事業が単独である場合には、サービス区分を設ける必要はないということでよいか。 | 同一拠点内に、複数の事業がなければサービス区分を設ける必要はありません。 |
| 86 | 運用指針Ⅰ-5-(2)では、「なお、特定の補助金等の使途を明確にするため、更に細分化することもできる」とあるが、サービス区分を必ず貸借対照表の作成単位としなければならないと解すべきか。 | 当該規定は、特定の資金の使途を明確にするために、サービス区分を細分化することを認める趣旨であり、サービス区分毎に貸借対照表を作成する必要はありません。 |
| 87 | 運用指針Ⅰ-5-(2)イにおいて、同一のサービス区分とすることができるものとして次のサービスを追加することはできないか。 ・指定通所介護と指定認知症対応型通所介護 ・指定介護予防通所介護と指定介護予防認知症対応型通所介護 | 運用方針5-(2)イでは、介護サービスと一体的に行われている介護予防サービスを想定しているところですが、左記のように介護予防ではなく、種別が相違する介護サービスについては、通常、別のサービス区分となります。 |
| 88 | 運用指針Ⅰの5サービス区分(2)サービス区分の方法 について 「なお、特定の補助金等により行われている事業において当該補助金等の収支状況を明らかにする必要がある場合等については、区分できるものとする。」とあるのはどのような趣旨か。 | 資金管理上必要な場合に、任意でサービス区分を更に細分化することができるという趣旨です。 |
財産目録
| NO. | 意見 | 回答(考え方) |
|---|---|---|
| 89 | 財産目録には、その使用目的も記載すべきではないか。 | 必要に応じて記載していただいても結構です。 |
| 90 | 財産目録が残ったままでは、計算書の簡素化に繋がらないのではないか。また、企業会計でも公益法人会計でも経営効率化のための重要な財務表として既に定着しているキャッシュフロー計算書の採用は、狙いである経営の効率化の実現の上で是非必要だと考えます。 | 財産目録は法律上作成義務があります。また、社会福祉法人における予算管理の重要性を考慮し、キャッシュフロー計算書ではなく、資金収支計算書を採用しています。 |
事業区分
| NO. | 意見 | 回答(考え方) |
|---|---|---|
| 91 | 福祉用具貸与事業と地域包括支援センター等について、事業区分の整理を教えて頂きたい。 | 「福祉用具貸与事業」は、社会福祉法に基づく社会福祉事業には該当しませんが、介護保険法に基づく事業であるため、「公益事業」として整理されるのが適当と考えています。 また、「地域包括支援センター運営事業」についても同様と考えています。 ただし、これらの事業が主たる事業である社会福祉事業と一体的に行われている場合は、社会福祉事業区分として処理することもできます。 |
| 92 | 診療所について、定款上は公益事業としてありますが、新会計基準では社会福祉事業区分ということでよろしいでしょうか。 | 定款上の公益事業であれば原則として公益事業区分となります。ただし、主たる事業である社会福祉事業と一体的に行われている小規模な公益事業は、会計基準上は社会福祉事業区分として処理することもできます。 |
| 93 | 資金収支計算書、事業活動計算書及び貸借対照表の作成区分が従来の2階層から3階層に変更されたことに伴い、より複雑化しています。 新基準の適用範囲の一元化と区分方法の変更は、社会福祉事業、公益事業及び収益事業を単一の社会福祉法人会計基準に一元化しようとする試みであると理解します。社会福祉法人会計の新基準の策定に当たっては、公益事業と収益事業をその範囲から除外し、三つの事業を営む社会福祉法人には現行の公益法人会計基準と企業会計基準を別個に適用する方針とするのが最良の方法と考えられます。 | 社会福祉事業、公益事業、収益事業を含めて、社会福祉法人全体としての経営状態を把握することが必要であると考えています。また、法人の事業内容により、財務諸表の省略を可能とするなど、事務の負担にも一定の配慮をしています。 |
資金収支計算書
| NO. | 意見 | 回答(考え方) |
|---|---|---|
| 94 | 資金収支計算書上の「差異」の計算の仕方は、「予算マイナス決算」とするのか、または、「決算マイナス予算」とするのか。 | 支出・費用において決算額が予算額を超えた場合を重視する立場から、予算マイナス決算とするものとします。 |
| 95 | 従来病院事業は病院会計準則により処理し、キャッシュフロー計算書を作成していました。そこで、事業によって、資金収支計算書かキャッシュフロー計算書の選択を可能とし、法人全体の資金収支計算書は作成しないこととして頂きたい。 | 社会福祉法人では予算管理の重要性が高いため、資金収支計算書を作成することとしています。 なお、病院等間の比較等のために社会福祉法人会計基準による財務諸表と併せて、キャッシュフロー計算書を作成していただくことを妨げるものではありません。 |
| 96 | 資金収支計算書はなぜ作成しなくてはいけないのか。 | 社会福祉法人では予算管理の重要性から、資金収支計算書を作成することとしています。 |
支払資金
| NO. | 意見 | 回答(考え方) |
|---|---|---|
| 97 | 会計基準(注6)について、「ただし、支払資金として流動資産及び流動負債には、1年基準により固定資産又は固定負債から振り返られたもの・・・を除くものとする。」とあるが、これには、固定資産たる「長期前払費用」から振り替えられ、流動資産に計上される「前払費用」が含まれることになる。一方で、前払による支払額で貸借対照表日の翌日から1年以内に行われる役務提供に係るもの(例えば翌年度4月分の家賃の支払い)についても「前払費用」として会計処理がなされ、この「前払費用」については、支払資金と解されるため、結果として、流動資産に計上される前払費用には、「支払資金たる前払費用」と「支払資金から除かれる前払費用」とが混在することになるので、財務諸表の明瞭表示の観点から、勘定科目を別にするなどの対応を取るべきであると考える。 | 日常的に発生するものではないので、勘定科目には記載してませんが、必要に応じ科目を追加してください。 |
| 98 | 会計基準第2章-2について、医薬品・診療療養費材料・給食用材料は貯蔵品に含まれるのか。就労支援会計のような販売目的では無いので、貯蔵品に含めた方が良いのではないか。 | 医薬品として棚卸を行うのは病院や老健のみで、一般の施設で保健室にあるような少額の医薬品は貯蔵品に含めて結構です。 |
| 99 | 会計基準第2章-2について、流動資産の繰延税金資産、流動負債の繰延税金負債を支払資金の範囲から明確に除外する規定が無いが、必要なのではないか。 | 流動資産の繰延税金資産、流動負債の繰延税金負債をを計上した場合は支払資金に含めます。 |
| 100 | 会計基準第2章-2について、「ただし、流動資産及び流動負債は1年基準により固定資産又は固定負債から振替えられたもの(略)を除く」という表現はおかしいのではないか。 | ご指摘を踏まえ「ただし、1年基準により固定資産又は固定負債から振替えられた流動資産・流動負債(略)を除く」に修正します。 |
重要性の原則
| NO. | 意見 | 回答(考え方) |
|---|---|---|
| 101 | 会計基準第1章2(4)重要性の原則について、個別の項目についての「重要性の乏しいもの」の判断基準は何か。 | 法人の規模等により判断基準が異なるため、一律にお示しすることは困難ですが、一般的には法人にとって重要か否か法人で判断していただくものと考えています。なお、所轄庁の指導がある場合にはそれに従ってください。 |
| 102 | 会計基準(注2)重要性の原則について、法人の判断基準を明確化していただきたい。 | 法人の規模等により判断基準が異なるため、一律にお示しすることは困難ですが、一般的には法人にとって重要か否か法人で判断していただくものと考えています。なお、所轄庁の指導がある場合にはそれに従ってください。 |
| 103 | 会計基準(注2)にある重要性の原則の適用の記述は、例示列挙か。 | 例示列挙です。 |
| 104 | 会計基準(注2)(2)において、「法人税等にかかる前払金、未払金、未収金、前受金等」に限定する必要はないのではないか。 | 「保険料~法人税にかかる」までがその後の「前払金~前受金等」までを修飾しています。 |
消費税
| NO. | 意見 | 回答(考え方) |
|---|---|---|
| 105 | 消費税の取り扱いについて、税込処理となっていますが、消費税率の変更により本来の収入、費用が分からなくなってしまう。税処理については選択としていただきたい。 | 消費税については税込処理を前提としていますが、法人として税抜き処理を選択することも可能です。 |
| 106 | 仮払消費税、仮受消費税、未払消費税など勘定科目が抜けているのではないか。 | 消費税関係は必要であれば中区分、小区分で科目を追加してください。 |
税効果会計
| NO. | 意見 | 回答(考え方) |
|---|---|---|
| 107 | 「繰延税金資産・負債」について、社会福祉法人において法人税が課せられる規模の収益事業を行う法人は少ない現状において、「繰延税金資産・負債」という法人税法上の収益事業についてのみ関係する科目が、流動資産・流動負債、固定資産・固定負債におかれている。 税効果会計を導入すべき事態が現実に存在していない状況で、単に可能性を有するというだけの理由で本来目的とする事業の重要科目と同等に並列されることは無用の混乱を招くことから、通常の勘定科目体系から外し、運用指針の中で「収益事業において法人税等が課せられ、なおかつその税効果にかかる会計処理を要する場合には『繰延税金資産・負債』の勘定科目を使用・・・」などの説明をおくことで十分と考える。 | ご指摘のとおり、「繰延税金資産・負債」に関する科目は削除した上で、運用指針20(5)において、使用する法人が追加する場合の方法について記述することとしました。 |
| 108 | 税と会計のタイミングの差を調整する会計が、税効果会計の本質とすれば、社会福祉法人は本来収益を目的にするものでなく、仮に収益事業を営むことがあったとしても、そのような調整が必要となることはないため不要なのではないか。 | 収益事業の規模等により調整が必要になることも想定して規定しています。 |
| 109 | 運用指針Ⅰ別添1について、租税公課の配分方法について、消費税の収入(売上)高による配分を加えて欲しい。 | 運用指針13において、別添1によりがたい場合は、実態に即した合理的な配分方法を認めています。 |
退職給付
| NO. | 意見 | 回答(考え方) |
|---|---|---|
| 110 | 退職給付会計について、退職給付金の給付を施設や事業所を通して行う場合、以下の処理が不明です。 (1) 給付金相当額が共済機関から入金されたときの処理の勘定科目「その他の収入(収益)」を使うのか、「預り金」等の流動負債勘定を使うのか。 (2) 退職給与引当金繰入、戻入の処理の勘定科目は想定しているのでしょうか。想定していないとすれば、どの様な勘定科目で処理をするのか。 | (1)「その他の収入(収益)」で結構です。 (2)退職給付引当金繰入は退職給付費用の一部になります。退職給付引当金の戻入は通常想定されないものと考えています。 |
| 111 | 運用指針Ⅰ-20-(2)-アについて、「退職一時金に係る債務について期末要支給額により算定することができるものとする。」とあるが、期末自己都合要支給額」「期末会社都合要支給額」のいずれか? | 自己都合要支給額により算定してください。 |
| 112 | 退職共済掛け金について、退職金が、①掛け金累計額より多く払われた場合、②掛け金累計額より少なく払われた場合の勘定科目を示してほしい。 | ①事業活動計算書では「退職給付費用」と「その他の収益」を、資金収支計算書では「退職給付支出」と「その他の収入」を使用してください。 ②事業活動計算書では「その他の費用」と「その他の収益」を、資金収支計算書では「退職給付支出」と「その他の収入」を使用してください。 |
棚卸資産
| NO. | 意見 | 回答(考え方) |
|---|---|---|
| 113 | 運用指針Ⅰ-16について、「原則として購入時に支出、販売時に費用処理」とあるが、購入時に費用処理できる場合はないのか。 | 重要性があるものを除いては、購入時に費用処理することができます。 |
弾力運用通知
| NO. | 意見 | 回答(考え方) |
|---|---|---|
| 114 | 投資有価証券の科目説明には長期保有とあるのみで、特定の目的を持って保有することは規定されていない。資金収支計算においては固定資産化することは資金外財産とすることであるから、有価証券を単に長期保有目的で購入したとするだけで当期末支払資金残高から外すことが出来るとすれば、当期末支払資金残高を30%以内とする行政指導は形骸化することになるがよいか。 また、老発第0312001号(社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について)は廃止されるのか。 | 「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」は存続します。 |
| 115 | 旧会計基準では、会計単位及び経理区分に「繰越金又は資金貸借の制限」が設けられていたが、新基準ではこのルール(制限)はどうなるのか。 | 「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」(局長通知)等でお示ししている、各区分間の繰り入れ及び貸し付け(繰り替え)の制限に変更はありません。 |
| 116 | 会計基準第4章-5「貸借対照表の種類及び様式」について、弾力運用通知により、社会福祉事業の運営費の繰入れ・貸付けが制限されているため、拠点区分別の計算書類より,むしろサービス区分別の計算書類の方が必要となる。 この確認のためには,サービス区分別の貸借対照表である「拠点区分貸借対照明細表」の作成も必要ではないか。 | 弾力運用通知の繰り入れ・貸し付けの状況は、「サービス区分間繰入金明細書」若しくは「サービス区分間貸付金(借入金)明細書」で確認することとなります。 |
注記
| NO. | 意見 | 回答(考え方) |
|---|---|---|
| 117 | 継続事業の前提に関する注記について、社会福祉法人がおこなう社会福祉事業は、事業の継続に関する疑義が生じた場合は、所轄庁の指導監督権限機能の発揮により、速やかな問題解決が図られるものと考えます。 そうであれば、当該注記については一般的な社会福祉法人においては、常に「該当なし」の記載をおこなうことになるはずであり、かえって注記をおこなうことで、ご利用者やご家族に事業継続に対し無用の不安を抱かせる原因ともなりますし、毎年「該当なし」の注記をおこなうこと自体が事務負担と業務効率を考えれば現実的では無いので、この注記については不要であり削除すべきではないかと考えます。 また、法人の行う一事業についての継続に疑義があるだけで、注記をしなくてはならないのか。 | 社会福祉法に基づく解散命令等、事業が継続されない状況も想定されることから、「継続事業の前提に関する注記」は必要であると考えていますが、事務連絡(Q&A)において、注記を要する事例を明記する予定です。 なお、本注記は、事業毎に判断するのではなく、法人として事業存続に疑義が生じた場合のみ注記していただくことなります。 |
| 118 | 運用指針Ⅰ「財務諸表注記」の記載例について、同一のサービス区分として差し支えないとされている「保育所を経営する事業と保育所で実施される地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業」がサービス区分の例として記載されているのは不適切ではないか。 | ご指摘の通り、「地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業」を削除しました。 |
| 119 | 財務諸表注記について、「事業所の名称並びに拠点区分・サービス区分」について会計基準(案)第5章(5)に“事業所の名称”とあるが、事業所の名称を注記に記載する必要はないのではないか。 | ご指摘のとおり、「事業所の名称」は削除します。 |
| 120 | 現行基準と新基準により追加された注記事項には、附属明細書への記載にふさわしい次のような多くの金額情報が含まれています。 ・基本財産の増減内容及び金額 ・基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し、その理由及 び金額 ・担保に供されている資産の種類・金額及び担保する債務の種類・金額 ・減価償却累計額と徴収不能引当金を直接控除した場合の期末残高等 ・満期保有債券の帳簿価額、評価損益等 ・国庫補助金等の内訳、増減額、残高等 ・関連当事者との取引内容 現行基準の注記事項と新基準で追加された注記事項を合わせると実に16項目の注記が必要となりますが、既述のとおり、財務諸表の内容を補足する注記事項のうち、金額情報については附属明細書に採り込むのがよいのではないか。 | 附属明細書は所轄庁への現況報告資料ではありませんので、財務諸表の一部である注記とは位置付けが異なります。また、附属明細書とするよりは、注記の方が負担が少ないと考えています。 |
| 121 | 財務諸表に対する注記について、財務諸表に対する注記は法人全体用と拠点区分用を作成することになっていますが、例えば、償却方法は、拠点区分ごと選択適用が可能であり、また、法人で採用する退職給付制度も拠点区分ごとに違う場合があると思われます。 拠点ごとに採用する会計方針及び制度が違う場合の法人全体用の記載例を明示していただきたく思います。 | 例えば、「A拠点:定額法、B拠点:定率法、C拠点:定額法」又は「定額法:A拠点、C拠点、定率法:B拠点」としても結構です。内容が分かれば結構ですので、形式は法人の任意です。 |
| 122 | 財務諸表の注記について、指針ではこれら注記については、法人全体と拠点単位と両方で記載することを求めている。拠点単位と法人全体と共通で両方で記載する項目も多い、拠点単位で記載すれば、法人全体の記載は一部省略が可能、あるいはその逆など、この部分は、実務的な合理化が行えるように見直していただきたい。 | 法人本部で各拠点区分の注記事項を把握するため法人全体の注記が必要になります。 |
| 123 | 財務諸表注記について「5.基本財産の増減の内容及び金額」の明細書の金額は、取得価額(減価償却等は考慮しない)なのでしょうか。それとも帳簿価額なのでしょうか。 | 帳簿価額でご記入ください。 |
| 124 | 財務諸表注記「固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高」について、「基本財産及びその他の固定資産の明細書」があるので不要ではないか。 | この注記は減価償却の脚注に代わるものですので必要です。また、附属明細書は現況報告資料でないため注記とは位置づけが違います。 |
| 125 | 財務諸表注記「満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益」について、時価及び評価損益は、参考数値として注記するという解釈でよいか。 | 参考情報として注記をお願いします。 |
| 126 | 保証債務等の偶発債務について、社会福祉事業を行う社会福祉法人にあたっては、保証債務の引き受けなどは想定されないのではないか。 | 「重要な偶発債務」という名称とし、法人が何らかの形で負う偶発債務があった場合に注記することを想定しています。 |
| 127 | 運用指針Ⅰ-22-(1)財務諸表注記「関連当事者との取引の内容」について、「対象とする役員は有給常勤役員に限定するものとする。」とあるが、注記の対象となる役員を有給常勤役員に限定する必要があるか。 | 役員としての報酬を受けていながらなおかつ取引を行うことへの妥当性の検証を行うため、有給役員に限定をしています。 |
| 128 | 関連当事者の範囲として、当該社会福祉法人の役員及びその近親者、前項の該当者が議決権の過半数を有している法人とありますが、近親者は、「3親等内の親族及びこの者と特別の関係にあるもの」とされており、広範囲で多岐にわたっていることから、関連当事者が議決権の過半数を有するかどうかを全て把握する事は不可能であると考えます。 更に「年間100万円を超える取引については全て開示対象とする」と運用指針(案)にありますが、地域社会と密着した事業展開をおこなってきた社会福祉法人においては、一般的に発生する取引であり、ほぼ全ての取引がこの要件に該当します。このような一種、過剰とも受け取れる規制については削除されるべきではないかと考えます。 | 関連当事者の注記の対象となるのは、「有給常勤職員」に限定されていますので、全ての役員について、「議決権の過半数を有しているかどうか」を確認する必要はありません。 また、「年間100万円を超える取引」については、社会福祉法人の事業規模を勘案して「年間1,000万円を超える取引」に修正します。 |
| 129 | 会計基準第5章(6)「基本財産の増減の内容及び金額」の注記に記入する金額は、簿価か、それとも取得価格か。 | 帳簿価格でご記入ください。 |
積立金
| NO. | 意見 | 回答(考え方) |
|---|---|---|
| 130 | 運用指針Ⅰ-19「積立資産の積立」について、専用の預金口座で管理しなくてよいのか。 | 本規定は、専用の預金口座で管理する場合の取扱いを示したものです。 |
| 131 | 会計基準第4章-4(4)「その他の積立金には、将来の特定の目的の費用又は損失に備えるため、・・・」とあるが、積立金の目的性の縛りをどの程度厳格にするのか明示すべきではないか。 | 「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」(平成16年3月12日雇児発第0312001号、社援発第0312001号、老発第0312001号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知)等で、既に明示しております。 |
| 132 | 運用指針Ⅰ-19「積立金と積立資産」について、「決算後2か月以内に行うものとする」とありますが、終期は示していますが始期が明確でありません。 | 専用の預金口座で管理する場合の積立時期の目安を規定したものです。また、規定を「遅くとも決算理事会終了後2ヶ月を超えないうちに」と修正します。 |
| 133 | 運用指針Ⅰ-19「積立金と積立資産」について「(1)積立資産の積立て」の文中に、「会計基準注解(注20)において積立金を計上する際は 同額の積立資産を積み立てることとしているが、資産管理上の理由等から積立資産の積立が必要とされる場合には、その名称・理由を明確化した上で積立金を積立てずに積立資産を計上できるもとする。」とありますが、資産管理上の理由等や積立金を積み立てずにとは何を指すのか具体的に記述していただきたい。 | 法人の判断で、流動資産を固定資産として、特定の目的のために、積み立てることを想定しています。 |
| 134 | 会計基準(注解20)について、「当期末繰越活動増減差額にその他の積立金取崩額を加算した額に余剰が生じた場合には・・・」とあるが、法人全体で余剰があれば、拠点区分別、サービス区分別には余剰がなくても、その区分での積立は可能なのか。 | 拠点区分単位で剰余金がない場合、当該拠点区分での積立はできません。 |
| 135 | 会計基準(注20)について、「積立金を計上する際は、積立の目的を示す名称を付し、同額の積立資金を積み立てるものとする」とあるが、旧基準では、積立貯金の積立は任意とされていたが、なぜ変更されたのか? | 積立金に対応した積立資産を持つことは、資産管理上必要であると考えています。なお、現行の指導指針でも同様の取扱いとしています。 |
| 136 | 会計基準(注20)について、積立資金の内容はどこまで許容されるのか。勘定科目説明には「現金預金等」としか記載されていないが、「安全確実」といった規定は、設けないのか。 | 「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局 長、児童家庭局長通知)第2の3「資産の管理」において、社会福祉法人の資産の管理は、安全、確実な方法で行うこととされています。 |
| 137 | 運用指針Ⅰ-19-(2)について、積立金は当該年度に積み立て、積立資産(預金)は翌年度の5月31日までに積み立てるとすれば、積立金と積立資産では、積み立てられる年度がずれるが良いか。 | 財務諸表へは当該年度に計上しますが、実務上、実際の口座への入金は、翌年度になることも可とするという趣旨です。 |
内部取引
| NO. | 意見 | 回答(考え方) |
|---|---|---|
| 138 | 財務諸表上に内部取引消去欄が出ているが、これは、どういう意味のものでどのように使用するものか。 | 内部取引消去は、同一法人内における各区分間の取引における二重計上を解消するためのものですので、正確な財務諸表を作成する観点からも、必要であると考えております。 |
| 139 | 会計基準(注解5)の「内部取引」の定義について明らかにしていただきたい。事業区分間、拠点区分間におけるすべての取引を内部取引と考えるのか?それとも従来の会計単位間あるいは経理区分間の資金繰入のような取引のみを指すのか? | 事業区分間、拠点区分間及びサービス区分間におけるすべての取引を内部取引として考えます。 |
引当金
| NO. | 意見 | 回答(考え方) |
|---|---|---|
| 140 | その他の引当金を廃止することにより、重要な引当金である修繕引当金までも廃止されることになる。修繕引当金も当期に発生していると見込まれる修繕費を計上するものであるため、廃止すべきではないのではないか。 | 「修繕を行うか否か」や「当期に発生していると見込まれる修繕費」は法人の任意で設定が可能であり、引当金にはなじまないものと思料します。積立金として計上いただくにはかまいません。 |
| 141 | 会計基準第4章3-(7)では、引当金残高の記載方法として、「・・・残高を負債の部又は資産の部の控除項目として計上するものとする」とあるが、 (注19)では「・・・残高を負債の部に計上又は資産の部に控除項目として記載する」となっており、表現が統一されていない。 | ご指摘のとおり、「・・・残高を負債の部に計上又は資産の部に控除項目として記載する」に統一します。 |
附属明細書
| NO. | 意見 | 回答(考え方) |
|---|---|---|
| 142 | 会計基準第6章2-(2)の「基本財産及びその他の固定資産の明細書」について、記載方法をより分かりやすくしてほしい。 | 事務連絡(Q&A)に記載する予定です。 |
| 143 | 運用指針Ⅰ-23別紙⑤「事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書」及び別紙⑩「サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書」について、借入日、返済予定日の記入ある方がよいのではないか。また、長期貸付を想定した表となっているが、資金の繰替使用は年度内に補てんしなければならないのではないのか。 | 年度末日の貸付金(借入金)残高の状況を確認するためのものですので、借入日、返済予定日は不要であると考えています。また、繰替使用の年度内補てんのルールには変更ありません。 |
| 144 | 附属明細書及び注記の種類が多く、負担が過大となりますので、整理、軽減をお願い致します。 | また、基準には、すべの事業種別を想定した注記や明細書を記載していますが、法人の規模や事業種別によっては、必要なものは一部になります。事業活動の透明性を図り、利用者等に対し、正確な財務状況を明らかにするためにも必要最小限のものであると考えておりますので、ご理解ください。 |
| 145 | 明細書上、「資金移動」という文言は、従来どおり「資金異動」とすべきではないか。 | より趣旨を明確にするため、「繰入金明細書」に名称変更しました。 |
| 146 | 附属明細書について、運用指針Ⅰ-23-(1)に掲げられている法人全体で作成する明細書は、拠点区分で明細を作らない限り法人全体のこれらの資金の把握は出来ないはずである。運用指針で示されているような法人全体で作成というのではなく、拠点単位での作成にするか(貸借対照表・財産目録も拠点単位となっている)、あるいは拠点で作成すれば全体で作成は一部は省略できるとすべきではないか。 | 法人全体の経営を把握するために必要であると考えています。 |
| 147 | 「サービス区分間繰入金明細書」および「サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書」において、特に想定される事業とはなにか。 | 措置施設、保育所等を想定しています。 |
| 148 | 会計基準第6章2-(2)の「基本財産及びその他の固定資産の明細書」、「引当金の明細書」について、拠点区分ごとに作成するものであると判断されるが、法人全体でも作成する必要があるか? | 拠点区分毎に作成していただければ結構です。 |
| 149 | 運用指針Ⅰ-23別紙①「借入金明細書」について、当初借入日も記載すべきではないか。また、元金償還補助金と利息補助金収入を統一すべきではないか。 | 従来の附属明細書にも記載の必要がなかったため、それを踏襲しています。また、「元金償還補助金」と「利息補助金収入」は別のものであると考えています。 |
| 150 | 運用指針Ⅰ-23別紙②「寄付金収益明細書」について、寄付者の属性ごとの会計で計上し、個々の寄付者の名前は不要ということでよろしいか。また、「法人の役職員」となっているが、役員と職員では属性がまったく異なるのではないか。 | 寄付者の個人名の記載を強制するものではありません。また、必要に応じて、役員と職員を分けていただいてもかまいません。 |
| 151 | 運用指針Ⅰの別紙⑲「授産事業費用明細書」について、「授産事業費用(5)=(1)・・・」でなく、「授産事業費用(6)=・・・」ではないか。 | ご指摘のとおり修正しました。 |
| 152 | 運用指針1-5(3)について、拠点区分事業活動明細書,拠点区分資金収支明細書は,いずれも制度会計上・管理会計上必要な明細書であるので省略すべきでないのではないか。 | 運用指針において、介護保険サービスと障害福祉サービス拠点では、拠点区分資金収支明細書を省略でき、保育所・措置施設については拠点区分事業活動計算書を省略できるとするなど、拠点の種類によって省略できる明細書を限定して、その有用性を損なわないように配慮していますので、問題はないものと考えています。なお、拠点区分事業活動明細書及び拠点区分資金収支明細書の両方を作成していただいてもかまいません。 |
| 153 | 運用指針Ⅰ-24「基本財産及びその他の固定資産は個々の資産の管理を行うため、固定資産管理台帳を作成するものとする」とあるが、固定資産管理台帳の様式は任意でよいか。また、付属明細書の「基本財産及びその他の固定資産明細書」との位置付けの違いはなにか。 | 様式は任意です。台帳は明細書の表示内容の詳細を補足するものです。 |
| 154 | 運用指針Ⅰ-23について、該当するものがない場合には、明細書を作成しなくてもよい旨を明記していただきたい。 | 運用指針23に、必要がない場合は附属明細書を省略できることを追加しました。 |
| 155 | 会計基準別紙4「○○拠点区分 事業活動明細書」について、「特別増減の部」以下が記載されていないのはなぜか。 | 経常的経費の収支を確認することを目的とした附属明細書であるため、このような取り扱いとしました。 |
| 156 | 新会計基準の貸借対照表科目では、ワン・イヤー・ルールによる勘定科目や棚卸資産の勘定科目が細分化され過ぎています。勘定科目の細分化は徒に日常の会計事務を煩雑化させます。せっかく附属明細表が導入されたのですから、貸借対照表科目のうち重要なものに限定して、その勘定科目の受払や残高の詳細を附属明細表で補う方法が良いと思います。 | 今回は様々な会計の基準を一元化し、大区分を事業ごとに分けましたので、勘定科目が多く見えますが、実際に1つの社会福祉法人で使用する勘定科目は一部に限られると考えています。 |
本部会計
| NO. | 意見 | 回答(考え方) |
|---|---|---|
| 157 | 本部会計は設ける必要があるのか。 | 理事会費用等、法人全体に係る費用を計上するため、本部会計は必要であると考えています。 |
| 158 | 運用指針Ⅰでは、法人本部に係る経費として理事会・評議員会の運営経費、役員報酬等が挙げられているが、広報や経理、人事労務管理に係る費用は法人本部に係る経費とならないのか。 | 運用指針の規定はあくまで例示であり、拠点区分やサービス区分に帰属しないものが本部の帰属となります。 |
有価証券
| NO. | 意見 | 回答(考え方) |
|---|---|---|
| 159 | 有価証券および投資有価証券において、満期保有目的の債券以外で市場価格があるものについては、時価をもって貸借対照表価額とすることとされ、勘定科目にも評価益、評価損が示されています。 社会福祉法人の場合は、ただちに売買・換金するとは考えにくく評価差額を当期の損益とすることは適切でないと思われます。特に、評価益については、保守主義の観点からも計上すべきではないと考えます。 | より正確な財務諸表とするために時価評価は必要であると考えています。 |
予算
| NO. | 意見 | 回答(考え方) |
|---|---|---|
| 160 | 運用指針Ⅰ-2-(2)において、編成した予算に基づいて事業活動を行うこととし、年度途中で予算との乖離等が見込まれる場合は補正予算を編成するものとするが、乖離額等が法人の運営に支障がなく、軽微な範囲にとどまる場合はこの限りではないとしている。 「軽微な範囲」について具体的基準が示されていないほか、「法人の運営に支障がなく」としてその判断を法人に委ねていることから、社会福祉法人の事業規模により「軽微」の概念が異なることも予想され、結果的に「予算に基づく事業活動」が疎かになることが危惧されるので、補正予算を編成しなければならない予算との乖離額等について、限度を示す必要があるのではないか。 | 一律に判断基準を示すことは困難ですが、例えば、適正な予算管理の元でも予測できなかった資金の収支が、決算時において結果的に発生したもの等であれば、仮に予算超過であったとしても、補正予算を編成しないことも考えられます。 一方、当初に予算計上されていない新規事業を年度途中に開始した場合や、減算処分を受けたこと等での収入減、年間予算に重大な影響を及ぼすような経費増加が明らかな場合について、これが予算に反映されていない場合は、補正予算を編成することが望ましいと考えられます。 |
| 161 | 予算書の様式を規定すべきではないか。 | 資金収支予算書は勘定科目が資金収支計算書の勘定科目に準拠していれば、様式は法人の任意といたします。 |
| 162 | 運用指針Ⅰ-2-(1)では、「資金収支予算書は各拠点区分ごとに収入支出予算を編成する」とあるが、本部会計をサービス区分とした場合、独立した予算書類が作成されないことにならないか。 | 法人として必要であれば、本部サービス区分の予算書を作成してください。 |
リース会計
| NO. | 意見 | 回答(考え方) |
|---|---|---|
| 163 | リース資産の減価償却方法がわからない。わかりやすく具体的に教えて欲しい。 | リース資産の減価償却方法は、以下のとおりです。 ①所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却は、自己所有の固定資産と同じ減価償却方法で算定してください。 ②所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却は、原則としてリース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定してください。 |
| 164 | 会計基準(注9)「リース取引に関する会計」に規定する「通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理」を行う場合、貸借対照表 上、「(大区分)固定負債(中区分)リース債務」を計上することになるが、当該「リース債務」の計上に伴う資金収支計算書上の勘定科目が設定されていない。 | リース債務は固定負債なので資金収支計算書には記載しません。必要に応じて、予算書の注記等に記載する方法などが考えられます。 |
| 165 | 運用指針Ⅱ-2「旧基準からの移行の場合」(4)ファイナンス・リース取引について、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う場合の調整で、①の原則的方法と思われる処理の計算方法について、リース資産の価額を(リース料総額から減価償却累計額を控除した金額)とされていますが、このリース料総額は利息相当額を含んだ金額なのかそれとも利息相当額を控除した金額なのかいずれでしょうか。 | 「リース料総額(現在価値に割引後)」と修正します。 |
| 166 | ファイナンス・リースに関して、運用指針Ⅱで「なお、リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で」とありますが、移行時の作業負担が過大となりますので、所有権移転ファイナンス・リース取引についても、移行時以前のものは移行時の経過措置として、引き続き賃貸借処理ができるようにお願い致します。 | 改正前のリース会計基準では、所有権移転ファイナンスリースは売買処理、所有権移転外ファイナンスリースは売買処理か賃貸借処理の選択制となっており、改正後に所有権移転外ファイナンスリースも売買処理を行うことになりました。この経緯を考慮すると、改正前は賃貸借取引を認めていた所有権移転外ファイナンスリースに賃貸借処理を認めることはできても、改正前から売買取引のみであった所有権移転ファイナンスリースにまで賃貸借取引を認めることは難しいものと考えています。その前提を明確にするために、「移行時の取扱い」2-(4)の「なお書き」を一部修正しました。 |
障害福祉
| NO. | 意見 | 回答(考え方) |
|---|---|---|
| 167 | 拠点区分の方法について以下の場合の取り扱いは、一体として運営される施設、事業所とみなしても構わないのかどうか教えて欲しい。 ① 障発第1206001号通知において示されている、同一敷地内の複数の、特定旧法指定施設が指定障害福祉サービス事業所へ転換する場合について、当該特定旧法指定施設としての指定の単位ごとに転換した場合。 ② 上記の例で同一の建物で障害者支援施設と、日中活動のみの生活介護を行う障害福祉サービス事業所に分かれて指定を受けているような場合。 ③ 障害者自立支援法施行前はもともと同じ施設の分場やデイサービス事業を行っていたが、障害者自立支援法に移行後、それ らの制度が無くなり、別の敷地や建物で別の事業所として指定を受けた障害福祉サービス事業所で、いずれも同じ者が管理者を兼務しており、一体として運営されている場合。 ④ 障害者支援施設等が地域福祉の推進のためにその利用者等の退所後の受け皿として、グループホームやケアホームを運営する場合。 | ①から④いずれも、法人で一体的に会計を処理することができれば1つの拠点区分とすることが可能です。 |
| 168 | サービス区分について 運用指針Ⅰ-5(2)において、障害福祉サービスにおいて実務上区分が困難な次のサービスを追加することはできないか。 ・居宅介護、重度訪問介護と行動援護 | 障害福祉サービスについては、基準省令上、各サービス毎に事業の会計を区分することを要請しています。これは、各サービスに応じて支援内容や利用対象者が異なり、それらに応じて報酬単価が設定されていることから、各サービス毎の収支状況を適切に把握する必要があるためです。 なお、他の事業と会計を区分する際、支出が一体不可分である場合は実態に即した合理的な按分方法を基本としていますが、収入按分等の簡便な方法でも差し支えありません。 |
| 169 | 運用指針Ⅰ-23(2)イ (エ)就労支援事業明細書(別紙➃又は⑱)を作成する場合の、下記の事業活動計算書の「就労支援事業費用」の部分と、資金収支計算書の「就労支援事業支出」の部分の科目出力例を例示してほしい。 就労支援事業費用就労支援販売原価 期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入原価 期末製品(商品)棚卸高 就労支援販管費 就労支援事業支出 就労支援販売支出 就労支援販管費支出 | 運用指針の別紙➃、⑱にて例示しました。 |
| 170 | 障害関係では、水道光熱費・燃料費・賃借料・雑費などを事務費・事業費で按分するように指導されているが、事業をするために使用されることが多く、按分する必要性がないのでは、科目を一本化していただきたい。 | 障害関係のみならず、措置施設等においても「事務費」又は「事業費」に区分することを要請しています。これは事業に係る運営費の収支を適切に把握することを目的としており、ご理解願います。 |
| 171 | .新会計基準とは離れるかもしれませんが、消費税についての意見を申し上げます。現在授産施設における作業収入に対して消費税の納付義務が課せられていますが、新体系の就労支援事業や生活介護事業における生産活動を行う場合の消費税についての判断基準が示されていないように思います。授産施設と違い、更生施設で行う作業に対しては、課税義務がありませんでしたので、生活介護事業において生産活動を行う場合、課税、非課税の判断ができずにいます。何らかの通知を出していただいた方が、事業者間に相違が発生せず公平になると思います。 | 消費税法により障害者自立支援法第5条第6項、第14項又は第15項に規定する生活介護、就労移行支援、就労継続支援において行う生産活動としての作業に基づき行われるものは課税の対象とされています。 |
| 172 | 別紙11から18まで就労支援に係る明細書が示されていますが、いずれも事業活動がベースになっています。 予算のこともありますが、それよりそもそも資金収支の内訳(説明)として、これらの別紙も存在する必要はないのでしょうか。 資金収支の就労支援事業支出の内訳(説明)は明細書から事業活動にのみ関係する科目を除いて把握し、資金収支の勘定科目は用いるが財務諸表はない。本当にこれでよいのでしょうか。 | 就労支援事業については、原価計算を主眼に置いているため、その計算に係る必要最小限の書類を作成するよう整理したため、資金収支計算の内訳表は不要としているところであり、ご理解ください。 |
| 173 | 就労支援事業について ①設備等整備積立金の取り扱いについては、現行基準どおりであり特段の変更点はないが、事業所の就労事業設備の整備規模に応じて、積立額及び上限額に幅を持たせるべきであると考えます。特に、資産更新時の補助の確約がない現状のままでは、上限は100%とすべきではないでしょうか。 ②現就労支援会計基準だと、「剰余金は利用者に還元しなければならない」となっているが、新会計基準になった場合、就労支援の収支としてみなくてもよいのでしょうか。 ③就労支援事業収支が経常活動による収支の中に入っているが、福祉活動と就労支援の収支が一緒になることによって分かりづらくなるように感じる。 ④固定資産の登録の範囲を明確にしてほしい。建物はどうするか…、備品はどこまでか…、減価償却費を就労支援の部での登録により就労支援収支差額が決定する。これにより利用者への工賃の支払いに影響が出る。 | ①就労支援事業は就労支援事業収入から必要経費を差し引いた額を利用者の工賃として支払うものとされていることから、原則として剰余金は発生するものではありませんが、安定的な利用者工賃等の支給を確保する観点から、一定の条件の下、例外的に積立金を認めています。この積立金については、利用者工賃等の支給額に影響を与えることから、慎重に検討していくことが必要であると考えています。 ②工賃計算の考え方については、剰余金は原則として利用者に還元することとしており、従前の考え方に変更はありません。 ③拠点区分の設定については、事業内容及び実施する事業の会計管理の実態を勘案して設定することとなっていますので、法人の判断により別拠点とすることは可能です。なお、就労支援事業の会計は、附属明細書において把握されるものであり、自立支援給付費等における福祉サービス(障害福祉サービス)事業の会計とは明確に区分されているところです。 ④固定資産の範囲については、減価償却の対象となる建物や備品等をその範囲としています。 |
| 174 | ・就労移行会計の部分は特に非常に分かりにくく、会計知識の無い理事の方などは理解することが不可能です。以前の授産会計基準での処理も引き続き認めて頂く様にお願いします。 | 障害者自立支援法における就労支援事業の会計処理については、原則として、「就労会計処理基準」の適用を受けることとなりますが、旧体系サービスを行う法人にあっては、経過措置として、従前からの基準である「授産施設会計基準」によることも差し支えないこととしています。 この経過措置を受けている法人が「社会福祉法人新会計基準」へ移行するに当たり、「授産施設会計基準」から「就労支援会計処理基準」、さらには「就労支援会計処理基準」から「社会福祉法人新会計基準」への移行と、度重なる会計基準の移行が必要であり、移行に係る事務負担が過重なものになることが考えられます。 こうしたことから、「社会福祉法人新会計基準」への円滑な移行を推進するため、経過措置として「授産施設会計基準」を採用している法人にあっては、「社会福祉法人新会計基準」に移行するまでの間に限り、新体系サービス移行後も「授産施設会計基準」によることができることとする予定でいます。 |
| 175 | 運用指針5-(3) 「障害福祉サービスを実施する拠点については、それぞれの事業ごとの事業活動状況を把握するため、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙 4)を作成するものとし、拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)の作成は省略することができる。」運用指針11 「また、拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、サービス区分の繰入金収入及び繰入金支出を記載するものとする。 作成される「拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)」は、経常増減差額までの記載しか求めておらず、サービス区分間繰入金収入及びサービス区分間繰入支出は記載されない。 すなわち、サービス区分間の資金移動はまったく認識されないがよいか。 | 障害福祉関係施設における拠点区分内でのサービス区分間の資金移動に制限はありません。 |
| 176 | 運用指針23-(2)-イ-(ア) 就労支援事業の範囲を定めるにあたり、障害者自立支援法及び同施行規則の定義によっているが、注解(注4)-(2)では、サービス区分を定めるにあたり指定基準によっている。おそらく同じであろうことを定義するのに別の言い方をしているのは何らかの理由があるのか。 | 注解4はサービス毎に会計を区分しなければならない規定の根拠を示しているものであり、就労支援事業の範囲を定める規定と異なります。 |
| 177 | 運用指針23-(3)-イ-(ウ)-③、23-(3)-イ-(エ) 多種少額の生産活動であること等を理由として、作業種別の区分及び製造原価と販売管理費と区分しないことを許容している。就労支援会計が導入されたときには、参入が想定される営利企業との競争をも考え、原価計算を適切におこなうべきとの考えがあったと理解しているが、これを放棄するのか。実務に大きなロードになることが想定される処理が他にも多々あるにもかかわらず、何故本件のみの安易な処理を許容するのか。「背 景と目的」にある、効率的な法人運営・正確な説明責任・効率性に関する情報の充実・事業活動状況の透明化等々に反するのではないか。 | 今回の見直しは、事業者の事務負担を軽減するためのものであり、原価計算の考え方を否定するものではありません。法人の判断により、従前のとおり厳密な原価計算を採用していただくことも差し支えありません。 |
| 178 | 「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18・9・29厚労省令第171号) §85にある「生産活動に係る事業のに必要な経費」の定義・例示等をすべきではないかどこまでを自立支援費で賄うのか明確に示すべきでは これなくしては、工賃倍増計画もありえないのでは | 生産活動に係る事業に必要な経費は、就労支援事業に関する附属明細書の勘定科目において示しており、従前の授産基準からの考えを踏襲しています。 |
| 179 | 「就労支援事業資産」の定義について 設備等整備積立金の積立上限額の算定基準となる「就労支援事業資産」の定義が、基準等のなかで示されていない。従前の就労支援事業会計処理基準では、「就労支援事業資産」について「基本財産以外」の固定資産が一定の基準を満たせば対象となりうる旨の定義(「『就労支援事業の会計処理の基準』に関するQ&A」のNo.50など)がされているが、実質的な線引きはきわめて不透明で拡大解釈の余地が大きくなっている。本来 の指定基準の要件(「就労支援事業収入」から「必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃と」する)を担保させる視点から、上限額は工賃変動積立金と同様に、就労支援事業の規模等により定めるほうが妥当ではないか。 | 就労支援事業資産とは、運用指針17(1)に定める減価償却資産のうち、就労支援事業の用に供する資産、かつ、5年以上の耐用年数がある資産をいいます。(ただし、建物は除く。) |
| 180 | 3、設備等整備積立金の上限額について 「就労支援事業」は、「原則として剰余金は生じない」という原則のなかで、例外規定のひとつとして「設備等整備積立金」としての積立が認められています。 しかし、その上限としている「就労支援事業資産」については具体的な説明がされておらず、「施設の大規模改修への国庫補助」のしくみがあることを「留意すること」とされています。つまり、施設の大規模修繕など、これまで国や事業者の責任で実施 されてきたことを就労支援事業収入でまかなうことが示唆されています。 就労支援事業は、法において「就労の機会、生産活動の機会の提供等を通じ」て、「自立した日常生活又は社会生活が営むことができる」ことを目的とした事業であり、国や事業者の役割が明示されている事業です。国や事業者の責任を、利用者に転嫁するような仕組みがつくることは、就労支援事業の社会的な役割を曖昧にするとともに、「原則、剰余金は生じない」という事業主旨 を空文化させ、利用者からの搾取を合理化する事態になりかねないことを危惧するものです。 | 就労支援事業は就労支援事業収入から必要経費を差し引いた額を利用者の工賃として支払うものとされていることから、設備等整備積立金は利用者工賃又は賃金の引上げやこれらの安定的な支給といった目的が達成されるための例外的な取扱いで す。 こうした趣旨を踏まえると、設備等の整備については、積立金のみに頼るのではなく、まずは国庫補助や機構の助成金等の既存の助成制度を有効に活用していただくことが必要であることから、このような留意事項を設けているところです。 |
| 181 | 貸借対照表について 就労支援事業収入における問題点として、法人として顧客宛に請求書を発行しているため、入金金額を事業ごとに管理するのは 不可能であり、事業所ごとで管理をする必要がありません。事業所ごとの財産状況は別途収支計算資料があるのですから、貸借対照表を事業所ごとに作成する必要があるのかが疑問です。 | 貸借対照表の作成は拠点区分単位毎の作成に止まり、サービス区分毎の作成は不要です。 |
| 182 | 事業間の資金の繰り入れについて 多機能型の事業所を運営しています(就労継続支援事業B型と生活介護)。B型のご利用者が多く、現在按分比について延べ利用者数を採用していますのでB型の支出が多くなっています。生活介護は単価が高くご利用者が少ないので支出が少なくなります。このような状況ですので、事業間で資金移動ができればと考えています。これは就労事業以外でも例えば居宅介護事業で移動支援事業と居宅介護事業を行っている場合でも事業間で資金移動ができればと考えています。 多機能型事業での事業間(新しい会計基準サービス区分になるのでしょうか)での資金の移動ができるようになればと思います。また現在それを扱う勘定科目がないのでその科目についてもご検討していただけたらと思います。 | 就労支援事業においては、各サービス毎に応じて工賃及び賃金を支払うことになっていることから、各事業間における資金移動は原則として想定していません。 なお、就労支援事業以外の社会福祉事業のサービス区分間における繰入金の状況については、附属明細書の別紙⑨「サービス区分間繰入金明細書」において把握することとして整理したところです。 |
| 183 | 就労継続支援A事業(利用者全員が雇用有りとする)において、就労支援事業収支差額が発生した場合、基準省令では、利用者工賃として分配する必要がない。(利用者賃金しか発生しないから。) その場合の当該収支差額について、適切な次期繰越方法ないし積立て方法を示した方が良いのではないか。厳格に全額を賃金として分配せよというのも厳し過ぎるし、かといってまったく賃金増を考慮しない経営も問題がある。そのバランスが自動的にとれるような会計処理が望まれる。(例えば「賃金変動準備積立金」などというもの。) また現在の基準省令のままでは、仮に就労A事業で雇用有り利用者が20人+雇用なし利用者が2人などという利用者構成だった場合、その年の経営状況によっては、雇用なし利用者へ支払われる工賃が巨額になるということも考えられる。よって必要によっては基準省令自体の見直しまたは補足も行い、適切な次期繰越方法ないし積立て方法を採用できるようにすべきである。 | 就労支援事業は就労支援事業収入から必要経費を差し引いた額を利用者の工賃として支払うものとされていることから、原則として剰余金は発生するものではありませんが、安定的な利用者工賃等の支給を確保する観点から、一定の条件の下、例外的に積立金を認めています。 就労継続支援A型の利用者賃金については、事業者との労働契約に基づいて賃金が支払われることとされていることから、必ずしも剰余金が発生しないとは言い切れませんが、利用者賃金の支給額に影響を与えることから、慎重に検討していくことが必要であると考えます。 |
| 184 | 積立金の流用について 就労支援事業では、指定基準において「就労支援事業収入」から「必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃と」する、としていることから、自立支援費収入の受取時期が「遅延」することを理由とした流用(繰替)を認めるというのは、論理が整合しないのではないか。 自立支援費収入は常に「2ヶ月以上遅延」で受領するしくみとなっているため、積立金の流用(繰替)を一時的なものにとどめるという努力義務を設けたとしても、結果的に自転車操業を助長するようなしくみになることが事態が懸念されないか。 | 工賃変動積立金及び設備等整備積立金に対応する資金の一部を一時繰替使用することは、自立支援給付費収入が安定的に確保される間までのやむを得ない取扱いとしています。 なお、繰替えて使用した資金は自立支援給付費収入により必ず補填することとしており、努力義務ではありません。 |
| 185 | 運用指針23-(2)-イ-(イ) 「就労支援事業活動明細書」 別紙➃、⑫ →ここでの「事業別」とは、(ウ)-③にでてくる作業種別のことと理解してよいのか。 | そのようににご理解いただいてかまいません。 |
| 186 | 運用指針23-(4)-イ-(エ) 「なお、この場合において・・・読み替えて作成するものとする」 →文言どおり読み替えても修正しきれないのではなく、すくなくとも「当期就労支援事業製造原価」を「当期就労支援事業費用」に読み替え、「就労支援販管費」は削除する必要があるのではないか。 | ご指摘を踏まえ、以下のとおり修正します。 「なお、この場合において、資金収支計算書上は「就労支援事業製造原価支出」を「就労支援事業支出」と読み替え、「就労支援事業販管費支出」を削除して作成するものとし、事業活動計算書上は「当期就労支援事業製造原価」を「就労支援事業費」と読み替え、「就労支援事業販管費」を削除して作成するものとする。また、別紙➃又は⑫の「就労支援事業別事業活動明細書」を作成の際には、同明細書上の「当期就労支援事業製造原価」を「就労支援事業費」と読み替え、「就労支援事業販管費」を削除して作成するものとする。」 |
| 187 | 明細書様式 別紙⑬、別紙⑭、別紙⑱ ○○拠点区分事業活動明細書(別紙4)の区分欄の○○事業、△△事業は指定障害者支援施設等では就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型等の各サービス区分を示しますが、別紙⑬、別紙⑭、別紙⑱の○○事業、△△事業は作業区分(木工事業、パン事業)の名称です。 ○○事業、△△事業は同じ名称ですが事業活動明細書(別紙4)と別紙⑬、別紙⑭、別紙⑱では違った内容なのです。上記3種類の別紙の就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型の各サービス区分に合計欄を設けてください。 | 合計欄は既に記載していますので、ご参照願います。 なお、就労支援事業における明細書上のサービス区分内に記載している「○○事業」、「△△事業」を「○○作業」、「△△作業」に修正します。 |
| 188 | 附属明細書のうち「就労支援事業に係る附属明細書」(以下「明細書」という)については、附属明細書ではなく、財務諸表として位置づけるべきではないかと考えています。 理由は、 ①実務上、「明細書」を作成するには、原始証憑から伝票を起票し、帳簿記録を行っていく必要があると思います。例えば、製造原価について、材料費、労務費、経費ごとに、その中で、細かく科目毎に記帳していく必要があります。 ②事業活動計算書について、科目説明の17ページを見ると小科目に「当期就労支援事業製造原価」が記載されていることから、①のように、記帳していくには、補助科目を用いらざるを得ないかと思います。 私が実務を行う場合には、補助科目を用いて作成していくと思います。 ③ただし、補助科目の使用は、任意です。 法人によっては、補助科目を用いずに、会計帳簿とは別のところで、把握して作成することも考えられます。法人によって処理が異なることになります。 ④ もし、補助科目を用いず、会計帳簿とは別に把握する形で「明細書」を作成していくことになると、次の問題も考えられます。 (1)実務上、製造原価に係る仕訳は、材料費、労務費、経費など、全て、例えば (借方)当期就労支援事業製造原価/(貸方)普通預金 と仕訳が行われることになります。 (2)会計帳簿と別のところで、把握した製造原価が、結果として「当期就労支援事業製造原価」となることから、正規の簿記の原則が求めている、「有機的一体となった帳簿組織から財務諸表を作成する」という観点からも問題がないか。 ⑤実務上の別の問題として、現行販売されている多くの会計ソフト(社会福祉法人向け)でも、補助科目の設定は、1階層であり ます。補助科目を用いる場合にも、できれば、階層は2つ持ちたい、例えば、1 材料費 2 当期材料仕入高ということも、実務的には問題になってきます。 以上より、企業会計における「製造原価報告書」のように財務諸表の一表として取り扱う方が、望ましいのではないかと考えます。 | 計算書類については、事務処理の簡素化を図る観点から、所轄庁への提出する書類である財務諸表を必要最小限にすることとし、それ以外の書類については所轄庁への提出書類の補足書類である附属明細書として整理しています。 こうした趣旨を踏まえ、就労支援事業に関する書類については、附属明細書として整理しているところであり、ご理解ください。 |
| 189 | 就労支援事業では、受託作業収入の施設等も多い。その場合、製造原価明細書を利用するのは、大げさで適切ではない。しかし、同一法人の他施設等の利用者が来て、作業を請け負うこともままある。 よって、販管費明細書にも外注費の中区分を設け、そこに「内部外注費」を設定できることを明記してはどうか。 | 障害関係のみならず、措置施設等においても「事務費」又は「事業費」に区分することを要請しています。これは事業に係る運営費の収支を適切に把握することを目的としており、ご理解願います。 「外注加工費」は一般的に製造原価に係る経費とされておりますので、「就労支援販管費明細書」に含めることはできません が、例えば「委託作業費」等、費目の分かる勘定科目を設定して処理することは差し支えありません。なお、一定規模の事業者であって、製造業務と販売業務に係る費用を区分することが困難な場合は、就労支援事業全体の明細書のみの作成でよいこととする予定です。 |
| 190 | 収支計算において、 現状科目ごとの按分処理は事務負担が大きく、確認作業にはさらに負荷がかかっております(事務作業の増加)。 直接原価項目の事業別支出は必要だと思いますが、光熱費や維持管理費まで作業収支として計算をする必要があるのか、疑問です。 新規作業科目の導入について、導入当初は赤字になる見込が非常に強いのですが、新規事業は赤字だから工賃の支給を抑えられる要因の恐れもあり、新規事業展開の抑制材料になりかねないと思います(新規作業導入の阻害 その1)。 逆にプラスになっている事業は、新規事業展開のための資金ストックができなくなってしまう恐れがあります(新規作業導入の阻害 その2)。 | 障害関係のみならず、措置施設等においても「事務費」又は「事業費」に区分することを要請しています。これは事業に係る運営費の収支を適切に把握することを目的としており、ご理解願います。 新規作業科目の導入の影響については、意見として伺います。 |
| 191 | ・ 旧法の通所授産施設です。まだ移行しておりませんので授産施設会計基準で処理しております。授産活動の規模は大きいので すが、それでも年間売り上げは1000万円以下です。一番大きな仕事はパンの製造販売ですが、関れる利用者は少ない為、パン以外に様々な仕事を提供しております。これを就労支援事業会計で処理するとなると、いったいいくつの事業に分かれるのでしょう か。こういった規模の小さな事業に見合った処理の仕方を考えていただけると助かります。分かりやすい、社会福祉法人共通の、会計基準を望みます。 | 就労支援事業に関する附属明細書については、原則として作業種別ごとに区分して表示する必要があります。ただ、作業種別ごとに区分することが困難な場合は、一部の附属明細書の簡略規定が定められています。 |
| 192 | 拠点区分別計算書の取扱について 定員40名以下の事業所について、拠点区分別事業活動明細書の作成は省略できるものとされたい。 | 現行の会計基準では、施設、事業所単位での財務状況が把握できないという問題がありましたが、拠点区分を設けることにより、施設、事業所単位での実態に即した運営管理が可能になると考えます。 |
| 193 | 新規作業科目企画等、多目的に使用できる積立金があるといいと思います。資金収支計算書の必要性について、収支計算は事業活動収支のみで良いと思います。 ※提案として 以前行っていた、措置費の会計基準が、経営判断をする上で簡潔で分かりやすいと思います。公金と事業収入の使途状況・財産状況も明確にできるため、理想的ではあると思います。ただし、以前の措置会計では、各事業所で貸借対照表の作成があったようですが、できる限り法人総括のみでの貸借対照表の作成が、合築型の事業所にとっては管理しやすいです(按分をしてしまうと、元帳等の帳簿管理等、日常業務でも非常にわかりづらいです)。 | 新会計基準では、積立金は、将来の特定の目的の費用又は損失に備えるための積立とされています。 また、一般的に社会福祉法人は公的資金・寄付金等を受け入れており、事業の効率性に関する情報の充実や事業活動状況の透明化が求められることからかんがみても、基準で定める通り、資金収支計算書の作成は必要不可欠と考えます。 |
| 194 | 就労支援の部分については、社会福祉法人のみならずNPO法人等の社会福祉法人以外の法人にも適用してほしい。また、既存の通知等との整理はいかがするのか。 | 社会福祉法人以外の法人が行う就労支援事業に関する会計処理については、これまでと同様に「就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて」(平成18年10月2日社援発第1002001号厚生労働省社会・援護局通知)を適用することとなりますが、本基準についても社会福祉法人新会計基準の改正内容に合わせた改正を予定しています。 また、今回の見直しに合わせ、関係通知やQ&Aの見直しも予定しています。 |
| 195 | 就労支援事業については、福祉サービス事業とは別の区分としていただきたい。 | 拠点区分の設定については、事業内容及び実施する事業の会計管理の実態を勘案して設定することとなっていますので、実態により別拠点とすることは可能です。 なお、就労支援事業の会計は、附属明細書において把握されるものであり、自立支援給付費等における福祉サービス(障害福祉サービス)事業の会計とは明確に区分されているところです。 |
| 196 | 多機能型事業所は一体的に運営しているため、現在の按分は複雑なだけで意味がない。このため、多機能型事業所については、事業別に処理するのではなく、多機能型事業所として会計を一本化してほしい。 | 障害福祉サービスについては、基準省令上、各サービス毎に事業の会計を区分することを要請しています。これは、各サービスに応じて支援内容や利用対象者が異なり、それらに応じた報酬単価を設定する必要があることから、各サービス毎の収支状況を適切に把握する必要があるためです。 なお、他の事業と会計を区分する際、支出が一体不可分である場合は実態に即した合理的な按分方法を基本としていますが、収入按分等の簡便な方法でも差し支えありません。 |
| 197 | 作業種目ごとの区分を困難な場合は省略できるようにしてほしい。 | ご指摘のとおり、「就労支援事業別事業活動明細書」についても、多種少額の生産活動を行う等の理由により、作業種別ごとに区分することが困難な場合は、作業種別ごとの区分を省略することができます。 |
| 198 | 現在の経済状況の中で、安定した工賃支給や設備投資等のための積立金、年度当初の運転資金など、会計の弾力的な運用について盛り込んでいただきたい。 | 就労支援事業は就労支援事業収入から必要経費を差し引いた額を利用者の工賃として支払うものとされていることから、原則として剰余金は発生するものではありませんが、安定的な利用者工賃等の支給を確保する観点から、一定の条件の下、例外的に積立金を認めています。この積立金については、利用者工賃等の支給額に影響を与えることから、今後、別途検討していくことが必要であると考えています。 |
| 199 | 現行の就労支援事業会計は按分が多すぎるように思える。 就労支援事業活動収支で作業種目毎に按分すると施設事業活動収支でも同じ縦軸で按分が発生し、その逆も然りである。そこまでの按分が本当に必要か疑問がある。 仮に按分が必要とした場合、按分比率の考え方が難しい。 人数按分とか作業面積按分とか按分の仕方は一応示されているが、実際利用者に支払っている工賃は評価により設定し支払っており、人数や作業面積等の按分方法では実態とあわないことの方が多い。 上記の按分方法は同額の工賃を支払っているなら通用する考え方だと思う。 | 経費の按分については、事業毎の収支状況を適切に把握することにより、事業の効率化等を図ることを目的としており、支出が一体不可分である場合は実態に即した合理的な按分方法を基本とし、これにより難い場合は収入按分等の簡便な方法でも差し支えありません。 |
| 200 | 新会計基準(案)において、就労支援事業明細書(簡略明細書)が作成できる事業所は、「就労支援事業年間売上高1千万円以下の事業所に適用」とされているが、この規定を緩和してほしい。 | 事務簡素化の観点から、適用範囲を「就労支援事業年間売上高5千万円以下の事業所」に緩和します。 |
その他
| NO. | 意見 | 回答(考え方) |
|---|---|---|
| 201 | 今回、制定される会計基準では、社会福祉法人はすべて同じ基準で決算書類等の作成を義務付けられると思います。しかし、規模の大きな法人もあれば小さな法人もあり一律で決算書類等の作成を義務付けることは小規模の法人に対して事務量の増加を招くだけであり、その分支援が手薄になることになると思います。そこで、規模に応じた決算書類等の作成の義務付けをお願いします。 | 小規模法人(社会福祉事業しか行っていない、又は拠点区分が1カ所である)の場合には、財務諸表の一部様式が省略できるなど、事務の簡素化にも一定の配慮をしています。 |
| 202 | 新会計基準の施行時にモデル経理規程の改訂はあるのでしょうか。 | 全国社会福祉協議会において、モデル経理規程の検討を行う予定です。 |
| 203 | 社会福祉法人に関る会計処理基準の一元化に際し、「企業会計原則及び公益法人会計基準に倣う」との基本的考え方については、社会福祉法人の特性を踏まえたものとするべきです。 | 公益法人会計基準や企業会計基準で行われている会計手法を参考にしながら、社会福祉法人の特性に合わせた会計基準を作成しております。 |
| 204 | 現行の社会福祉法人会計基準と指導指針との関りでは、介護保険制度見直しにより会計処理上の疑義・改正が生じた際に、社会・援護局所管の法人会計基準と老健局所管の指導指針の調整が必要となるために迅速な対応が出来ないことが度々あった。そのため実務の現場では会計処理が遅れる状況が続いたのである。 会計基準一元化の今後、各種別事業の制度改正が会計基準の勘定科目体系並びに会計処理方法に関連する指導、又は各種別の会計処理に係る疑義に対しての回答をするにあたり、関係各局(部)間で滞りなく対処されるようにされたい。 | 新会計基準の制定により、会計処理方法が統一化されることで、ご指摘の点は解決されると考えています。 |
| 205 | 社会福祉法人会計基準及び注解に関して、通知発出後の実務上の対応をどのように行っていく予定か。国際会計基準等の影響で企業会計の見直しの頻度が上がっているため、例えば適用指針、Q&Aなどを発行していく予定があるか。 | 必要に応じて、事務連絡(Q&A)を発出する予定です。 |
| 206 | 第1章2-(2)について、「財務諸表は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳した会計帳簿に基づいて作成しなければならない。」とあるが、実務の現場では会計ソフトの導入によって、伝票起票はおこなわれず、いきなり総勘定元帳に記帳する処理が行われているのが実態である。これに対応した、基準・規定とすべきではないか。 | ソフトの使用の有無にかかわらず、会計基準は会計処理の原則をお示しするものです。 |
| 207 | 運用指針Ⅰ-15-(1)「自転車競技法第12条の16第1項第7号」とあるが、法律改正があり、該当条文はないのではないか。 | ご指摘のとおり、「自転車競技法第24条第6号」と修正します。 |
| 208 | 運用指針Ⅰ-15-(1)「いわゆる民間公益補助事業による助成金等を含むものとする。」とあるが、「いわゆる民間公益補助事業」の定義とはなにか。 | 公益を目的として、社会福祉法人を含む一般に広く公募されている助成金を想定しています。 |
| 209 | 運用指針Ⅰ別紙の明細書のうち、就労支援事業製造原価明細書(別紙⑬・⑭)、就労支援事業販管費明細書(別紙⑮・⑯)、就労支援事業明細書 (別紙➃・⑱)、授産事業費用明細書(別紙⑲)における「国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)」の金額の表示について、マイナス表示して加算するのか、プラス表示して控除するのか、具体的に金額を例示してほしい。 | マイナス(△)表示して加算するものとします。 |
| 210 | 病院・診療所を経営する社会福祉法人は、従来、新病院会計準則又は旧病院会計準則に準拠して会計処理を行っており、今後も他の医療機関との比較のために大枠では病院会計準則に則った会計ルールでの会計情報の作成が必要となる可能性があります。病院会計準則に則った財務諸表と社会福祉法人会計基準に則った財務諸表の二種類の作成を求められることのないよう、統一方針のご提示をお願い致します。 | 病院準則は、設置主体の会計基準を適用することを前提としているため、社会福祉法人が設置主体である場合には、社会福祉法人会計基準を適用することは、病院準則の考え方と合致したものと考えています。 |
| 211 | 会計基準第2章-5に、次の規定を設ける必要はないか。 「事業活動資金収支差額、施設整備等資金収支差額及びその他の活動資金収支差額を合計して当期資金収支差額合計を記載し、これに前期末支払資金を加算して当期末支払資金残高として記載するものとする。」 | ご指摘を踏まえ、会計基準第2章-5(4)に追加しました。 |
| 212 | 財団法人立の保育所は、公益法人会計基準と社会福祉法人会計基準のどちらを適用するのか。 | 社会福祉法人以外の者が保育所を経営する事業を行っている場合は、それぞれの会計基準による会計処理を行って頂いて構いませんが、保育所運営費の弾力運用の実施状況を把握するため、社会福祉法人会計基準による資金収支計算書等を作成する必要があります。 |
このページの内容は、他の制度通知や条文4コマでもつながっています:
▶︎ 会計基準・通知一覧ページへ戻る
▶︎ 4コマで読む社会福祉法人会計基準(条文別まとめ)はこちら
社会福祉法人会計基準と関係通知
厚生労働省令 社会福祉法人会計基準と関係通知をご参考に記載しています。
名称または略称のところのリンクから、①~④の各ページに進みます。
| 区分 | 名 称 | HP上の略称 |
| ① | 社会福祉法人会計基準 平成二十八年厚生労働省令第七十九号(改正施行日: 令和元年五月七日) | 会計基準 |
| ② | 社会福祉法人会計基準の運用上の取り扱い (令和2年9月11日付け厚生労働省通知) | 運用上の 取り扱い |
| ③ | 社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 (平成3 1 年3 月2 9 日付け厚生労働省通知) | 運用上の 留意事項 |
| ④ | 社会福祉法人会計基準のパブリックコメント(回答) | パブリックコメント |
勘定科目の説明
計算書類の様式
社会福祉法人会計基準の計算書類の様式を参考に記載しています(e-gov 法令検索)
| 区 分 | 法人単位 | 事業別内訳書 | 拠点別内訳書 | 拠点区分 |
| 資金収支計算書 | 第一号第一様式 | 第一号第二様式 | 第一号第三様式 | 第一号第四様式 |
| 事業活動計算書 | 第二号第一様式 | 第二号第二様式 | 第ニ号第三様式 | 第二号第四様式 |
| 貸借対照表 | 第三号第一様式 | 第三号第二様式 | 第一号第三様式 | 第三号第四様式 |
まんがの部屋
事務所の記事が600記事になってきました。会計をさらに親しみやすくなるように、記事の漫画化を進めています。
ぜひご覧になってくださいね。
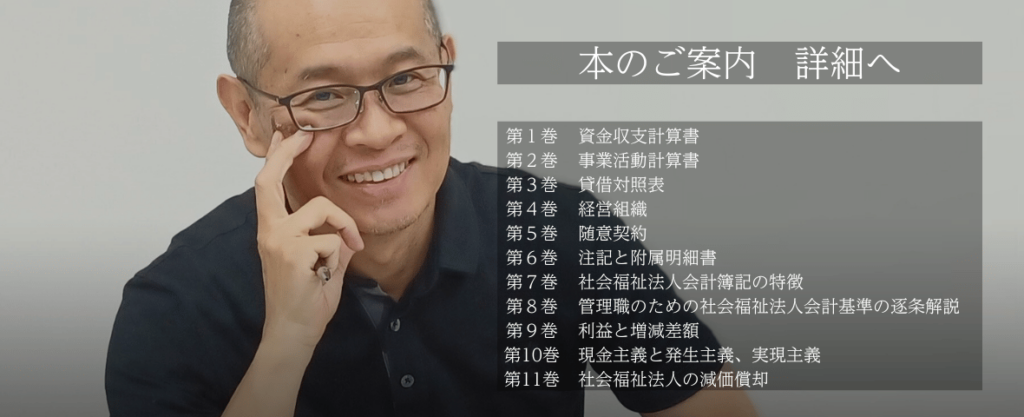
マツオカ会計事務所のストーリー
よかった。ありがとう。読んだ人が幸せでありますように。
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。